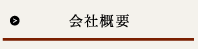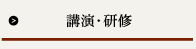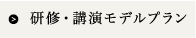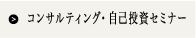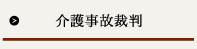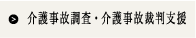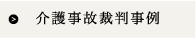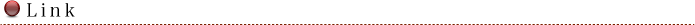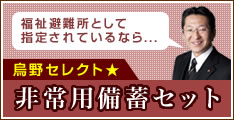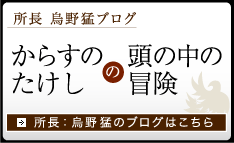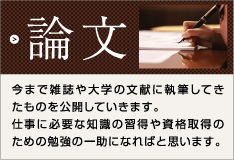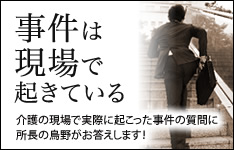- TOP
- 事件は現場で起きている
- Q1〜Q10
質問内容をクリックすると答えが開きます。
>> Q11〜Q20へ >> Q21〜Q30へ >> Q31〜Q40へ >> Q41〜Q50へ >> Q51〜Q60へ >> Q61〜Q70へ
Q1. 土地や山などの不動産を多く所有していた利用者さんが亡くなりました。介護事故での死亡ではありません。死亡そのものについては親族間での争いはないのですが、遺言書が2通出てきて、1通は「全財産長男に」というもの。2通目は「全財産次男に」という内容です。当然、認知症状があったので、遺言を書いた時に認知症があったのかどうかという点で、長男からは「介護記録を見せろ」という訴えがあり、次男からは、「長男から介護記録を見せろ、と言われても絶対に見せないでくれ」と言って来られました。
どうすればいいでしょうか?
A1. 大変難しい問題ですね。まず、遺言については、何通書いても良いことになっています。通常、直近に書いた遺言書が有効になるのですが、認知症状のある利用者さんの場合の遺言書については、遺言内容作成時において、意思能力・判断能力の有無が争点になります。
認知症があれば遺言書を書くことができないという意味ではありません。遺言に求められる能力は、高度な判断能力が求められるわけではなく、それよりも若干低い能力である意思能力程度でよいとされています。ですから、遺言ができる能力は、未成年でありながらも15歳以上と、民法でもゆるい規定になっています。
次に、認知症の方には遺言能力がない、つまり書いた遺言書はすべて無効になるのか、という点です。認知症であっても、「本心に復している」状況にある場合には有効です。その「本心に復しているか否か」の判断に、介護記録が非常に重要になってきます。
最後に、介護記録をどの親族の範囲にまで開示することができるのか? とくに、今回のように親族間で全く逆の対応を法人に求めてきた場合、どうすればいいのでしょうか?
介護の領域では、介護記録の開示や開示範囲について、いまだ十分に論議がなされていないように思いますが、医療領域ではインフォームドコンセントの流れを受けて、記録の開示・開示範囲について学会でもガイドラインが出されています。それによると、「該当する本人と最も交渉の程度が密な者」の意見が重視されるものとなっています。
今回の質問のケースで言えば、遺産という親族間の争いに法人が巻き込まれてしまったという構図ですが、死亡した利用者と長男・次男との交渉程度を法人が判断し、その選択結果を長男・次男にも通知するところまでしか、法人としての役割はないと思われます。その結果、長男・次男どちらかが法人に対して異議を申し立ててきたとしても、法人側に違法性はありません。
Q2. 介護事故が起きた場合に、介護にあたった職員個々の責任は問われるのでしょうか ?
A2. 法人内で事故が起こった場合の責任の所在について、①職員に課せられる責任と、②法人に課せられる責任、とに分けて解説したいと思います。
まず、介護サービスを提供する場合、「誰と誰との契約なのか」という視点から考えてください。
当然、利用者本人と法人との契約ですね。場合によっては利用者ではなく、利用者の親族らを代理人として(法的な代理人ではない)署名・押印することも多々ありますが…。
ようするに、法人と契約をするということは(一度施設に置いてある契約書をご覧になってください)法人のトップつまり社会福祉法人である場合は理事長が利用者と契約を結ぶということになります。
しかし、利用者と理事長が契約を結んだとしても、直接理事長が食事介助や入浴介助をするわけじゃありませんよね。介護職員がそれら諸々の業務を日々こなすわけですよね。つまり介護職員は、契約の当事者である理事長の代わりに利用者に対して介護サービスを提供するわけです。介護職員は、理事長からすると履行補助者という位置づけになり、履行補助者である介護職員の過失によって事故を招いた場合、利用者と介護職員との間には直接的な契約関係はないわけですから、介護職員個人が契約に基づく責任を問われることはありません。契約の当事者である法人トップの責任、つまり理事長の責任と言うことになります。
しかし、虐待など明らかに介護職員による過失で事故が起ったような場合には、介護職員に賠償責任が課せられ、さらに介護職員を監督する立場の法人のトップも使用者責任を問われることになります。
そしてこの介護職員とは、単に正社員(常勤)の職員という意味だけではなく、例えボランティアや実習生による無償の活動であったとしても、法人側には責任が求められます。その責任の程度は、正規の介護職員に課せられるほどの高い注意義務までは求められないにしても、「善良なる管理者の注意義務」(略称「善管注意義務」民法第400条)を負うとされています。
こうした施設内での介護事故に関しては、介助時また介助時以外(介助中ではなく、例えば利用者が一人で転倒したような、介護職員が関わっていない場合)、どちらにしても同じ責任が法人には求められます。
Q3. 私の施設では、記録の方法として「毎日のサービス実施」をチェックリストにして「○」「×」式のコメントをする方式を採っています。例えば、「皮膚のかぶれの軽減」に対しては、「○」…清拭しました。「スタッフ同士で日々のコミュニケーションをとっている」に対しては、「○」…申し送りの際に疑問点を聞きました。 このようなチェックリストによる記入方法で、記録の代用になるものなのか、教えてください。
A3. はじめに、「毎日のサービス実施」をチェックリストにして、「○」「×」にする方式は、サービスの質をある一定程度に均一化するためには非常に有効だと思います。
ただし、以下の点に気をつけてください。
そのチェックリストの項目に対して、その項目の存在意味を考えてください。何を目的として、何を裏付けるための項目であるのか、このチェックリスト全体が一体何を意味し、このチェックリストすべてに「○」が入ることで、どこまでのサービスの質を担保することができるのか?
言い換えれば、このチックリストの項目の内容、表現、項目の分類方法等のチョイスが一番難しいところなんですね。欲を言えば、現場の介護スタッフの多くが関わりながらこのチェックリストが作成されたとするならば、作成過程の中で、「こういう場合には○? それとも×?」といった話し合いが持たれているはずですから、「○」や「×」の根拠も自然と明らかになってきます。そうすれば、精度の高いより良いサービスを実施するためのチェックリストとなります。
つまり、「○」や「×」をつける際に、その根拠が非常に大切になってきますから、数回、また数日、今のチェックリストで試した後、各リーダー級のスタッフは、「○」の根拠、「×」の根拠を正確に把握しておく必要があります。
たとえば、福祉サービスの第三者評価項目をみてもそうですが、たとえば「ホームページはありますか?」という項目については、ホームページにかける費用や、更新等の手間を問うことが目的ではなく、まだサービスを利用していない利用者や家族、そして既にサービスを利用している者、そして地域社会に対して、法人が十分な説明義務を果たしているのか? ということが項目から聞きたいことの目的なんです。
ですから、「ホームページがありますか?」と言う問いについては、あるから「○」ではなく、「ホームページ更新の頻度」、「各種イベントについての最新の記事の掲載」、「現在法人が取組んでいること(もちろん、完成したものでなくても、途中のもので結構です)」などがアップされていることが求められているんです。
これらの点に注意しながら、「毎日のサービス実施チェックリスト」を意味のあるもの、継続的に発展させていけるものに作り上げていって下さいね。
最後に、「このようなチェックリストによる記入方法で、記録の代用になるものなのか?」というご質問でしたね。結論からいうと、記録の代用にはなりません。記録を書くための材料には十分なりますし、記録を裏付けるための資料として役立ちますが、記録は記録として残す必要がありますね。
記録の書き方につきましては、先回の東京と岡山でお話ししました講義レジメを参考にしてください。
Q4. 施設内で事故が起こった際、事故に遭遇したスタッフ当人は、家族の謝罪等には関わらせず、上席の者が謝罪の担当として関わっていました。今後も同じような事故が発生した場合の謝罪については、誰が適任なのでしょうか?
A4. これも難しい質問ですね。以前にも皆さんにはお伝えしました通り、介護施設内では、必ず事故は起きます! これが前提です!
ただ、事故は起きるものなんですが、大切なのは、次の二点です。
一つ目は、事故を起こさないために、どのような取組を現在実施しているのか?
二つ目は、事故が起きた際、誰に情報を一本化して、誰を通して、誰(とくに家族)にまでその情報を伝達するのか…。 その二点です。
今回のご質問は、二点目の「事故が起きた際に…」というものですよね。
まず施設内で介護事故が起こったような場合には、はじめに徹底した事実確認を行うことです。「誰が悪かったのか? 誰がミスをしたのか?」という犯人探しではなく、法人として事実関係をしっかりと掴んでおくことが必要です。とくに家族はいろんな人に事故当時の様子について聞きたいと思っていますから、複数のスタッフが事実関係が曖昧なままで回答すると、微妙なズレだけが家族側の記憶に残り、その結果、「施設は嘘をついている!」という誤解を招いてしまうからです。ですから情報は誰かに一本化し、家族からの対応についても、窓口を一つにしておく必要があります。
それと「家族への説明について、誰が適任なのか?」という点においては、やはり事故に直接遭遇したスタッフよりも、上席の者が対応した方が、いらぬ感情が入らず冷静に対応できると思います。それぞれの法人で、窓口が生活相談員であったり、施設ケアマネであったり、事務長や副施設長であったりしますが、事故の情報を正確に把握し、十分な説明ができる方であればどなたでもいいと思われます。
ただ、介護事故で亡くなられたケースと、損害保険等で十分に対応できると思われるケースとでは、法人として「誰を出すか?」に違いがあってしかるべきです。
はじめからキングを出すと後が続かなくなりますからね…。
Q5. 今の利用契約書には利用料を滞納した場合の規定がありません。現在利用料金を滞納している方への対応と、今後、利用者さんからの利用料の滞納があった場合にはどうすればいいでしょうか?
A5. このような問題は、今後ますます増えてくると思われますね。
まず、「サービス利用契約書」や「重要説明書」等に利用者さんが支払うべき支払い義務の規定がなくても、法人が介護サービスを提供している以上、利用者さんが法人に対して利用料金の支払義務があるのは当然のことです。おそらく、身元保証人の方や、身元引受人の方が当人の介護サービス利用の際の契約書に名前が載せられていると思いますが、その保証人の方や引受人の方に当人の未納分利用料金を支払ってもらう手もありますが、彼らに利用料金を立て替えて支払う法的義務まではありません(彼らが善意で支払ってくれれば良いのですが…)。なので、法人側としては、保証人や引受人に事情を説明して当事者に代わって支払ってもらえるかどうかをお願いすることまではできますが、法人側に請求するだけの権利があるかといえば、NOです。手続き的に言えば、入所施設であれば施設からの退去を求め、民事上、未払い分の利用料金を強制的に取り立てることは法的には可能です。実情としても待機の高齢者が非常に多く存在する中、きちんと支払ってもらえるであろう利用者さんを確保することは、法人経営として当然のことですから。
しかし、そうした場合の裁判費用や時間的手続き的な手間の問題だけではなく、物理的に強制執行することは法的にはできるものの現実問題としては難しいでしょうね。
現在のところ法人側としてとれるリスクヘッジとしては、成年後見制度の利用しかないと思われますが、利用料金滞納の事実経緯が、ご本人の年金等の資力が枯渇したのか、親族等に年金通帳を含めた金銭管理を依頼していたにもかかわらず、当の親族が使い込んでしまい利用料金が支払えないのか、等の確認が急がれます。また、たとえ適切な後見人が見つかりそうな場合であったとしても、実際の成年後見制度の利用については、管理費と言いますか手数料といいますか、月に数万円程度かかることが予想されますので、資産の乏しい高齢者には現実的に利用できる制度ではないかもしれません。
ご質問の答えになりますが、現在もう既に滞納している利用者さんの場合には、上記の理由から、今のところ打つ手がない様に思われます(生活保護という手続きの方法もないわけではありませんが…)。そして現在、滞納についての利用料金徴収の記載が「契約書」「重要事項説明書」になく、今後、滞納する利用者さんが現れるリスクを回避するには、早急に利用料金についての規定を契約書上明記し、かつ親族等に対して利用料金が滞った場合に代わりに支払ってもらえるような拘束力のある文章を交わしておくことをお勧めします。
Q6. 施設内ボランティアの養成講座の中で、亡くなった入所者の方の事例を取り扱った際「個人が特定できる」と受講者であるボランティアの方からクレームを受けました。当日の資料の記載は「Aさん 女性 認知症の87歳」といった具合に、個人が特定できないように施したつもりでしたが、取り扱った事例の内容自体がかなり具体的なケースであったため、補足として口頭での説明を加えた際、個人が容易に特定できる結果となってしまいました。このボランティア養成講座の受講者は事例の当事者である故人の友人であり、この指摘を受けて、ご家族に説明とお詫びに行きました。その際、家族の方からはかなり感情的に「残っているサービス提供にかかる個人情報(故人の基本情報や介護記録等)を破棄、もしくは見せて欲しい」という強い要望がありました。この破棄については、監督官庁である保険者に相談したところ、2年間は保管義務があるので、破棄すべきではないと言われました。また、「見せて欲しい」という要求には、利用者さんの家族に対する悪い感情(誰も面会に来てくれない、年金手帳を嫁に取り上げられたなど…)まで記録しているため、家族の方が見た場合、気分を害される恐れがあります。どうすればいいのでしょうか?
A6. さて、亡くなられた方の個人情報保護に関するご質問ですね。
結論から言いますと、家族の方から当事者についての個人情報に関する諸々のものを破棄して欲しい、という訴えがあった場合、監督官庁である保険者が言うような一定期間の保管義務について、介護保険法上筋が通っているように思われます。しかし、最近の判例等の流れを見てみますと、個人(自己)情報の開示請求と言う視点から見ますと、家族の方の言っていることに従った方がいいように思われます。
ただ、破棄ではなく、家族の方にお返しするという方が良いかと思われます。この場合の家族とは、おそらく亡くなられた利用者さんと最も密な接触のあった親族と考えていますが…。その際、記録やメモ等の中に、返却(開示)したことで何か不都合な点があるようでしたら、返却は時として大きなリスクにつながり、記録上の些細な表現方法から、油に火を注ぐ結果になりかねません。家族の方への返却が難しいような場合には、内々にコピーを取っておき、内部文書として保管、当事者である家族の方の言うように、「原本は破棄した」とお伝えするのがよろしいかと思います。この故人についての自己情報の開示につきましても、生存されている場合と同様の取扱いが必要となってきます。最悪、名誉棄損という訴えも故人(遺族)に対して当てはまりますので…。また、「介護記録等を見せて欲しい」という点につきましては、個人(自己)情報の開示請求でありますことから、憲法21条に規定する「知る権利」に該当するものです。ですから、どのような記録の内容であったとしても、法人として記録を開示する法的義務があります。ただしこの場合、家族の方には「ご覧になった場合、ご家族の方が気分を害される内容まで記録されていますが…」という一言を付け加えてお見せするのがベターかと思われます。
Q7. 身体拘束についていつも頭を悩ませています。施設の中でも認知症の方が非常に多く、また要介護度も重度化する傾向がある中、利用者さんの身体を拘束せずに、かつ転倒や転落の事故を予防し、利用者や家族からは最高の介護を求められる…。「そんなの、できない !」と思いつつ、毎日途方にくれながら介護をしています。
先生、助けてください
A7. 日々の業務、本当にお疲れ様です。私もいつも考えています。いったいどこまでの介護が求められるのか? 高齢者になるまでは、社会から疎外されていたような人が、いざ高齢者になり施設に入った途端、至れり尽くせりの介護を受けることができ、その延長線上で、ベッドを壁側につけただけでも身体拘束である、と行政からも指導を受け、かつ家族からは事故があった場合、「元気だったあの頃のおばあちゃんに戻してくれ!」と罵詈雑言を浴びせられ……。
ごめんなさい、ごめんなさい、身体拘束についてのご質問でしたね。ちょうどつい最近、身体拘束をめぐる最高裁での判決が出されました。これまでは精神病院を舞台とした身体拘束に関する裁判がほとんどであり、最高裁まで進んだような事例はなかったのですが、今回の事例は精神科病院ではなく、介護施設や医療機関での初めての身体拘束裁判であり、かつ最高裁にまで進み判決が下された点で、非常に意味のある事例です。
事件の概要は、事故当時80歳であった高齢女性は、意識混濁や精神運動興奮、錯覚、幻覚を伴う可逆的意識障害と診断されたせん妄状態で、一般病院に入院し治療を受けていましたが、興奮しベッドから起き上がろうとする動作を頻繁に繰り返したため、看護師が抑制具であるミトンを使用して、高齢女性の両手をベッドの両側の柵にくくりつけました。その2時間後、高齢女性の入眠を確認してミトンを外したという事実について、高齢女性と家族が両上肢をベッドに拘束したことは、診療契約上の義務に違反する違法な行為であるとして争ったものです。
同じ材料をもって争った裁判であるにもかかわらず、高等裁判所と最高裁判所とでは、観る角度が違うんでしょうね。判決文をそのまま載せますので、法律用語やその言い回しに、難しさを感じるかもしれませんが、お付き合い下さい。
名古屋高等裁判所は、「患者の夜間せん妄は高齢の上、頻尿で排尿について過度に神経質になっていたころに入眠剤マイスリーの投薬中止もしくはリーゼへの切り替えによる不眠とオムツへの排泄を強いられたことへのストレスなどが加わって起きたものであり、当直看護師の必ずしも適切でない対応もあって、それが治まることなく、時間の経過とともに高まったものと認められ、患者のせん妄に対する対応としての身体拘束に切迫性、非代替性があるとは直ちに認められない上、患者の排尿やオムツへのこだわりを和らげ、落ち着かせて入眠するのを待つ対応が不可能であったとは考えられないなどとして緊急避難行為として例外的に許される場合に該当するといえるような事情も認められないと判示し、本件拘束の違法性を認める。」という内容でした。
しかし最高裁判所では、「入院患者の身体拘束は、その患者の受傷を防止するなどのために必要やむを得ないと認められる場合にのみ許容されるものであるが、患者は当時80歳という高齢で、他病院で4か月前に転倒して骨折しており、10日程前にもせん妄状態で転倒したことがあったこと、看護師らは4時間にもわたって患者の求めに応じて汚れていなくてもオムツを交換するなどしたが、患者の興奮状態は収まらず、また、勤務体制からして深夜長時間にわたり看護師が患者に付きっきりで対応することは困難であったこと、看護師が患者の入眠を確認して速やかにミトンを外したため、拘束時間は約2時間であったことなどの事情の下では、本件抑制行為は患者が転倒、転落により重大な傷害を負う危険を避けるため緊急やむを得ず行われた行為であって、診療契約上の義務に違反するものではないと判断する。」というものでした。
最高裁のこの判決によって、現在の介護・医療水準と人員や設備、運営といった規程の中での身体拘束をめぐる法的判断が確定したといえます。
この最高裁判決で、特筆するところは、まず、そもそも身体拘束は必要やむを得ないと認められる場合にのみ許される、という前提を踏まえた上で、身体拘束が例外的に許される①「切迫性」、②「非代替性」、③「一時性」を入院していた高齢女性の実情から判断し、かつ、当該病院に入院する前の病院でも転倒し骨折していること、また、身体拘束があった日の10日程前にも転倒があったことなどをあげています。
ここ最近の特別養護老人ホームの裁判事例でも、誤嚥による度重なる急変に対しての対処の甘さから厳しい判断を下したもの(東京地裁平成19年5月28日判決)や、グループホームでの度重なる転倒転落による事故に対して、十分な措置を講じなかった点に大きなペナルティーを課したもの(大阪地裁平成19年11月7日判決)があります。
施設に入所している高齢者は、認知症や寝たきりのため、ほとんどの高齢者に何かがあった場合、大きな負傷につながることが事前に予想されることから、事故があった場合の次への対処方法や方策の取り方が争点になってきます。
今回のご質問や、最高裁が下した身体拘束についてのとらえ方についても、身体拘束が許されるための条件を正確に見極め、「適切な拘束」をする状況も今後、必然的に発生するものと思われます。その「適切な拘束」をするための見極めと解除のタイミング、そして同じ事故を何度も起こさないための取組みが大切ですね。
「どんな犬でも、一度は咬む」 アメリカの「ことわざ」です。
一度目は大目に見てくれますが、二度目は許されない、という意味だそうです。「先生、助けてください…」に対する答えです。「いつも助けてあげますよ。ただ、いつも精一杯の介護をしててください。その努力をどう挙証資料として表面化させるか。そのことを一緒になって考えていきますから…」
Q8. 利用者さんが「ここ(特養)を出て行きます!」と言って、娘さんが迎えに来て一緒に退所していったのですが、他の親族が、「そんなはずはないから、もう一度施設(特養)に戻すように!」と行ってきました。施設には新しい入所者さんが入ってこられて満床で待機の状態です。
こんな場合、どうしたらいいんでしょうか? 先生、助けてください!
A8. 入所契約の解除に関する問題ですね。いずれにしても、利用者ご本人の意思能力と言いますか、判断能力が争点になったご相談ですね。
皆さんが勤めていらっしゃる特別養護老人ホームでは顕著にあることですが、「帰りたい」であるだとか、「お父ちゃんが迎えに来るから、家に帰ります(配偶者は既に亡くなっている)」と言った帰宅願望の方のこういった発言はよくあることですね。しかし、今回のケースでは、おそらく身元引受人と思われる娘さんが一緒に来て退去の手続きをして帰った、ということですから、利用者さんご本人だけが「帰ります」と言ったような認知症の方の帰宅願望とは訳が違うと考えたわけですよね。
いくつかポイントとなる点がありますが、まず利用者さんの年齢、認知症状態などから、ご本人の発言が本心であるのか?
と言った点ですね。特別養護老人ホームの実態からは、死亡や長期入院が見込まれるケース以外での退所というのは比較的考えにくいものですから、相談者であるあなたは、娘さんが引き取るのではないか? と思った結果、利用者さんの「ここを出て行きます!」という言葉で退所の手続きを進めたんでしょうね。
その後、他の親族が全く逆のことを施設に対して求めてきたわけですよね。となりますと、利用者さんが入所に至る経緯、家族(親族)関係等に関するアセスメントの不十分さが気になるところですね。
そして、この「娘」の存在です。この娘というのは、利用者さんとの関係で言えば、「代理人」なのか、「身元引受人」なのか、「保証人」なのか、という点です。よく、「代理人」という言葉を皆さんが使われるのを耳にするのですが、代理人とは正確には「法定代理人」のことを指し、「後見人」とイコールの存在です。つまり、法的な手続きを経た法的に権限を持った人間ということになります。おそらく「娘」は、そこまでの権限をもった代理人ではないと思われます。また「身元引受人」にしても、文字通り引受人ですから、単に身柄を引き取るだけしかできず、法人としてもそれ以上を請求することはできないということです。
蛇足ですが、例えば、滞納している利用料を引受人に支払ってもらうなどの請求は残念ながらできませんし、また、利用者が滞納している場合に、「利用者に代わって引受人が支払うように」という書面での同意書があったとしても、それらの同意書は法律上まったく効果がなく無効となってしまいます(ですが、家族はそれらのことを知らないので、同意書はとらないよりはとっておいた方がいいですが…)。
今回のケースでは、入所予定である高齢者の入所前におけるアセスメントだけではなく、むしろ利用者さんを取巻く家族や親族間の問題が争点ですね。施設を含む法人が、利用者を含む家族の情報をどこまで入手しておく必要があるのかについては、非常に難しいところですが、入所契約の際の家族の位置づけについて、「代理人」「身元引受人」「保証人」等の規定を再度整理しておく必要がありますね。その際に、家族の誰にどこまでの権限があるのか、法人の方でガイドラインを示し、それを入所の際に家族にも理解してもらっておく必要があったかと思われます。
想像の域を超えませんが、利用者の方に動産・不動産等の資産があり、誰がそれを管理するのか、といった点での揉め事がこのケースの背景にあるように思われてなりません。
今回のケースでは、特別養護老人ホームにおいての相談でしたが、有料老人ホームのような入居一時金や、毎月の利用料が高額になるような施設などでは、この「入居契約解除の日」が、払戻金との関係で非常に重要なポイントになることが予想されますので、お気をつけください。
今後、入所者である高齢者だけの問題ではなく、彼らを取り巻く家族・親族間のトラブルが急増するものと思われます。利用者を取り巻く遺言、相続、扶養、親族間の確執などなど…、法人内でも施設ケアマネだけでは解決しきれず、また生活相談員だけでも頭を悩ます問題が、マグマが噴火するように皆さんの頭の上に火の粉が降りかかります。それをどうやって消火し、マグマの必要以上の噴火を押えるのか…。皆さんのこれまでの経験と知識を駆使した腕の見せ所ですよ。
Q9. 利用者さんが入所される前に、クレジットで何かを買い続けていたようです。クレジット会社(信販会社)から利用者ご本人に何度か連絡をしたようですが、施設入所になっているので連絡がとれず、利用者さんの親族に確認の電話が入ったようです。先日、親族の方がお見えになって、クレジットのローンを利用者さんである母親の年金から支払ったら、毎月の施設への利用料が払えない、という訴えがありました。
親族の方が言うには、「母親が認知症でボケている! ということが証明されれば、クレジットの方は支払わなくてもいいかも知れない」とおっしゃるのですが…。
こんな場合、どうすればいいのでしょうか?
Q9. 今後、このようなクレジットといいますか、ローン問題は多くなってくると思われます。高齢者である利用者も、保護の対象としてだけではなく、商取引の当事者として購買者という位置づけが濃厚になってくるように思われますから。
さて、今回のご相談ですが、初期の認知症だったかも知れない高齢者(入所前の購入ということで)が、クレジットを利用して商品を購入した場合、何を買われたのか、というより「いくら程の商品」を買ったのか、という点がひっかかりますね。軽い認知症に罹患している高齢者は、外部の人からみると、ある部分ではしっかりとしているように見えるものです。健康器具(磁器マット入り布団など)や、高額な健康食品等を買ってしまうなどの被害が消費生活センターのまとめなどでも多くなっていると聞きます。
クレジットで商品を購入するとは、たとえば訪問販売員などが高齢者に商品を売り付けた場合、その商品代金を信販会社が販売者に購入者に代わって支払い、信販会社は購入者に対して与信調査をしたうえで金利を乗せて支払わせる、という流れをとります。その際、販売員が購入者が高齢で判断能力の低下を利用して騙すように買わせたのであれば、明らかに違法性が疑われますし(ただし、立証が難しい)、また信販会社も電話等での与信調査の段階で、高齢者が高額な商品を購入しようとする場合には、それなりの注意が必要になります。
つまり法的には、販売会社および信販会社が過量販売ないし過剰与信をおこなったとみなされ、公序良俗に反し契約そのものが無効になる可能性が非常に高いということです。ですから、親族の方が「認知症であることが証明できれば、クレジットの残金を支払わなくてもいいかも…」と言ったことに対してはその通りなのですが、先にも触れましたように、その立証が非常に難しいので、そう簡単にはいかないように思われます。
その余波を受けて、今度は利用料が支払えない、というのは頭を抱える問題ですよね。「このような問題は家族間で解決して下さい」と言いたいところですが、利用料を滞納し始めれば、法人としても事情を聴く必要が生じますし、問題解決に向けての助言も家族側からは求められるでしょうから…。
先程の話に戻りますが、クレジット会社や信販会社には、一般論として顧客の年齢や職業、収入や資産状況、顧客の生活状況および顧客とのこれまでの取引状況等を考え合わせ、顧客に対する不当な過量販売その他適合性の原則から著しく逸脱した取引をしてはならないとされていますし、また不当に過大な与信をしてはならない信義則上の原則を負っています。
ですが、割賦販売法38条は割賦購入斡旋業者に対して、過剰与信防止義務が認められる前提となる法制度が未だ整備されていない状況ですし、店舗内における過剰売買に関する規制も十分ではないという限界もあります。一般の商取引においても限界を抱える問題が、施設に持ち込まれるとは、これまでの高齢者施設の中ではあまり想定されていなかったケースですね。
Q10. 私の施設では、記録の方法として「毎日のサービス実施」をチェックリストにして「○」「×」式のコメントをする方式を採っています。例えば、「皮膚のかぶれの軽減」に対しては、「○」…清拭しました。「スタッフ同士で日々のコミュニケーションをとっている」に対しては、「○」…申し送りの際に疑問点を聞きました。 このようなチェックリストによる記入方法で、記録の代用になるものなのか、教えてください。
A10. これまで、介護事故といえば、介護スタッフが利用者さんの介助中に誤って転倒・転落させてしまったり、また職員が見ていないところでの怪我であったり、と言うのが一般的でしたよね。
しかし、今後は利用者さん同士による事故が十分に考えられますし、その際の法人側(施設)の責任が問われてくるケースが多発するように思われます。これまでも利用者さん同士による事故がなかったわけではないんでしょうが、そこは両方の家族側が、当事者同士のことを「お互いにボケてるんだから、仕方がないですし、お互い様ですよ」と、害を加えた高齢者と害を被った高齢者、そして施設といった三者関係の修復は、被害にあった高齢者が死亡したりしない限りにおいては、穏便に解決されていた場合が多かったです。
しかし、死亡まではいかなくとも、入院等で医療費がかさんだり、今回のケースのようにショートの利用者さんが頚部骨折等で入院し、退院してからも在宅介護が難しくなり、施設入所しかないといった重症化した場合などは、今後の受け皿との関係で、両方の家族のストレスや欝憤が一気に施設に向けられることが多くなってくるものと思われます。
結論から言うと、今回のケースでは、法人側の入所者の管理についての適切な管理を行わなかった安全配慮義務違反の有無が問われることになると思われます。
両者に判断能力があるような場合の事件では、単純に傷害事件という形で処理できるのですが、認知症の高齢者同士の傷害事件となると、保育所や幼稚園での子ども同士の喧嘩で怪我をさせた・怪我をした場合と同様、成人か未成年かはともかくとして、責任を問えない者同士の争いとなりますから、争いのあった「場所」が主な責任主体としてクローズアップされるようになります。
この場合のリスクを考える上での前提条件として、加害者である入所者の認知症男性について、日常生活状況の把握が最も重要になってくると思われます。認知症の程度や暴言も含めた暴力行為の頻度、内容、時間帯、誘発させる要因に何らかのパターンがあるのか等です。
また、事故当時の介護スタッフの配置状況、関わり方も重要です。加害者である入所男性と、被害者であるシュート利用の高齢者が、施設内のどこの場所で接点があったのか? 加害者側の男性高齢者が自分の車椅子だと思い込み、被害者である高齢女性を突き飛ばす前に、おそらく何らかの事故を予見できる兆候があったと思われます。例えば、被害女性が乗っていた車椅子の取手の部分を揺さぶったであるだとか、また被害女性に大きな声で暴言があったであるだとか…。そのような事故を予見するような状況をスタッフが認識していたのか、と言う点については、事故発生時のその場、またはその場近くに、介護スタッフがどのような配置で一体何をしているところだったのかが争点になります。
さらに、介護スタッフが、事故の当事者同士の状況を予見できていたのであれば、次ぎにスタッフはどのような行為でトラブルを回避しようと試みたのか、が争点となります。たとえば、加害男性を自分の部屋、もしくはフロアに帰るように促したのか、逆に、被害女性を加害男性から遠ざけるために、違うフロアや階、部屋に移動させたのか、といった点です。
予見可能性と回避義務については、過失を構成する重要な要素ですからね。
そして最後に、事故発生後、加害者・被害者共の家族に誰がどう電話等で説明したのか、が問題となります。事故発生後どれくらいの時間が経過した時点で連絡をしたのか、連絡した際には、事実確認が十分にできた上での情報提供だったのか、その情報提供の際に、事故の当事者である被害者と加害者の二人の関係だけで発生したことを強調したのか、つまり当事者同士の関係だけを強調してしまった結果、どちらかの家族、もしくは両方の家族に、施設側(法人)が責任を転嫁しているかのような誤解を与える内容、もしくは伝え方になっていなかったか、などの点に注意しなければなりません。
はじめにもお伝えしましたとおり、法人側には、入所者の管理についての適切な管理を行わなかった安全配慮義務違反が問われることになります。その際、適切な管理の下、十分とは言えないまでも、当時の介護スタッフの人員、配置、彼らの判断や行動が、ある一定程度の安全を確保し、他の方法ではなく、選択した行為がより妥当であったということが第三者に説明でき、それを記録として文章化できるようにまでしておく発想が必要だと思います。