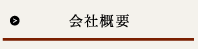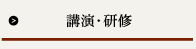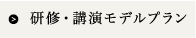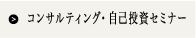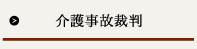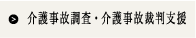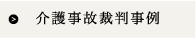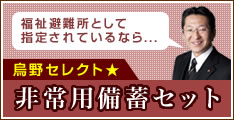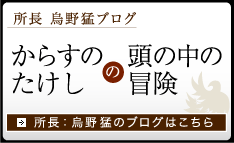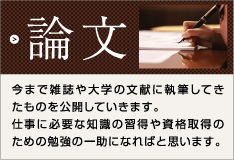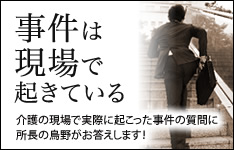- TOP
- 事件は現場で起きている
- 介護事故
質問内容をクリックすると答えが開きます。
>>クレーム >> 職員教育・研修 >> 契約関係 >> 災害 >> 労務管理
Q2. 介護事故が起きた場合に、介護にあたった職員個々の責任は問われるのでしょうか ?
A2. 法人内で事故が起こった場合の責任の所在について、①職員に課せられる責任と、②法人に課せられる責任、とに分けて解説したいと思います。
まず、介護サービスを提供する場合、「誰と誰との契約なのか」という視点から考えてください。
当然、利用者本人と法人との契約ですね。場合によっては利用者ではなく、利用者の親族らを代理人として(法的な代理人ではない)署名・押印することも多々ありますが…。
ようするに、法人と契約をするということは(一度施設に置いてある契約書をご覧になってください)法人のトップつまり社会福祉法人である場合は理事長が利用者と契約を結ぶということになります。
しかし、利用者と理事長が契約を結んだとしても、直接理事長が食事介助や入浴介助をするわけじゃありませんよね。介護職員がそれら諸々の業務を日々こなすわけですよね。つまり介護職員は、契約の当事者である理事長の代わりに利用者に対して介護サービスを提供するわけです。介護職員は、理事長からすると履行補助者という位置づけになり、履行補助者である介護職員の過失によって事故を招いた場合、利用者と介護職員との間には直接的な契約関係はないわけですから、介護職員個人が契約に基づく責任を問われることはありません。契約の当事者である法人トップの責任、つまり理事長の責任と言うことになります。
しかし、虐待など明らかに介護職員による過失で事故が起ったような場合には、介護職員に賠償責任が課せられ、さらに介護職員を監督する立場の法人のトップも使用者責任を問われることになります。
そしてこの介護職員とは、単に正社員(常勤)の職員という意味だけではなく、例えボランティアや実習生による無償の活動であったとしても、法人側には責任が求められます。その責任の程度は、正規の介護職員に課せられるほどの高い注意義務までは求められないにしても、「善良なる管理者の注意義務」(略称「善管注意義務」民法第400条)を負うとされています。
こうした施設内での介護事故に関しては、介助時また介助時以外(介助中ではなく、例えば利用者が一人で転倒したような、介護職員が関わっていない場合)、どちらにしても同じ責任が法人には求められます。
Q4. 施設内で事故が起こった際、事故に遭遇したスタッフ当人は、家族の謝罪等には関わらせず、上席の者が謝罪の担当として関わっていました。今後も同じような事故が発生した場合の謝罪については、誰が適任なのでしょうか?
A4. これも難しい質問ですね。以前にも皆さんにはお伝えしました通り、介護施設内では、必ず事故は起きます! これが前提です!
ただ、事故は起きるものなんですが、大切なのは、次の二点です。
一つ目は、事故を起こさないために、どのような取組を現在実施しているのか?
二つ目は、事故が起きた際、誰に情報を一本化して、誰を通して、誰(とくに家族)にまでその情報を伝達するのか…。 その二点です。
今回のご質問は、二点目の「事故が起きた際に…」というものですよね。
まず施設内で介護事故が起こったような場合には、はじめに徹底した事実確認を行うことです。「誰が悪かったのか? 誰がミスをしたのか?」という犯人探しではなく、法人として事実関係をしっかりと掴んでおくことが必要です。とくに家族はいろんな人に事故当時の様子について聞きたいと思っていますから、複数のスタッフが事実関係が曖昧なままで回答すると、微妙なズレだけが家族側の記憶に残り、その結果、「施設は嘘をついている!」という誤解を招いてしまうからです。ですから情報は誰かに一本化し、家族からの対応についても、窓口を一つにしておく必要があります。
それと「家族への説明について、誰が適任なのか?」という点においては、やはり事故に直接遭遇したスタッフよりも、上席の者が対応した方が、いらぬ感情が入らず冷静に対応できると思います。それぞれの法人で、窓口が生活相談員であったり、施設ケアマネであったり、事務長や副施設長であったりしますが、事故の情報を正確に把握し、十分な説明ができる方であればどなたでもいいと思われます。
ただ、介護事故で亡くなられたケースと、損害保険等で十分に対応できると思われるケースとでは、法人として「誰を出すか?」に違いがあってしかるべきです。
はじめからキングを出すと後が続かなくなりますからね…。
Q7. 身体拘束についていつも頭を悩ませています。施設の中でも認知症の方が非常に多く、また要介護度も重度化する傾向がある中、利用者さんの身体を拘束せずに、かつ転倒や転落の事故を予防し、利用者や家族からは最高の介護を求められる…。「そんなの、できない !」と思いつつ、毎日途方にくれながら介護をしています。
先生、助けてください
A7. 日々の業務、本当にお疲れ様です。私もいつも考えています。いったいどこまでの介護が求められるのか? 高齢者になるまでは、社会から疎外されていたような人が、いざ高齢者になり施設に入った途端、至れり尽くせりの介護を受けることができ、その延長線上で、ベッドを壁側につけただけでも身体拘束である、と行政からも指導を受け、かつ家族からは事故があった場合、「元気だったあの頃のおばあちゃんに戻してくれ!」と罵詈雑言を浴びせられ……。
ごめんなさい、ごめんなさい、身体拘束についてのご質問でしたね。ちょうどつい最近、身体拘束をめぐる最高裁での判決が出されました。これまでは精神病院を舞台とした身体拘束に関する裁判がほとんどであり、最高裁まで進んだような事例はなかったのですが、今回の事例は精神科病院ではなく、介護施設や医療機関での初めての身体拘束裁判であり、かつ最高裁にまで進み判決が下された点で、非常に意味のある事例です。
事件の概要は、事故当時80歳であった高齢女性は、意識混濁や精神運動興奮、錯覚、幻覚を伴う可逆的意識障害と診断されたせん妄状態で、一般病院に入院し治療を受けていましたが、興奮しベッドから起き上がろうとする動作を頻繁に繰り返したため、看護師が抑制具であるミトンを使用して、高齢女性の両手をベッドの両側の柵にくくりつけました。その2時間後、高齢女性の入眠を確認してミトンを外したという事実について、高齢女性と家族が両上肢をベッドに拘束したことは、診療契約上の義務に違反する違法な行為であるとして争ったものです。
同じ材料をもって争った裁判であるにもかかわらず、高等裁判所と最高裁判所とでは、観る角度が違うんでしょうね。判決文をそのまま載せますので、法律用語やその言い回しに、難しさを感じるかもしれませんが、お付き合い下さい。
名古屋高等裁判所は、「患者の夜間せん妄は高齢の上、頻尿で排尿について過度に神経質になっていたころに入眠剤マイスリーの投薬中止もしくはリーゼへの切り替えによる不眠とオムツへの排泄を強いられたことへのストレスなどが加わって起きたものであり、当直看護師の必ずしも適切でない対応もあって、それが治まることなく、時間の経過とともに高まったものと認められ、患者のせん妄に対する対応としての身体拘束に切迫性、非代替性があるとは直ちに認められない上、患者の排尿やオムツへのこだわりを和らげ、落ち着かせて入眠するのを待つ対応が不可能であったとは考えられないなどとして緊急避難行為として例外的に許される場合に該当するといえるような事情も認められないと判示し、本件拘束の違法性を認める。」という内容でした。
しかし最高裁判所では、「入院患者の身体拘束は、その患者の受傷を防止するなどのために必要やむを得ないと認められる場合にのみ許容されるものであるが、患者は当時80歳という高齢で、他病院で4か月前に転倒して骨折しており、10日程前にもせん妄状態で転倒したことがあったこと、看護師らは4時間にもわたって患者の求めに応じて汚れていなくてもオムツを交換するなどしたが、患者の興奮状態は収まらず、また、勤務体制からして深夜長時間にわたり看護師が患者に付きっきりで対応することは困難であったこと、看護師が患者の入眠を確認して速やかにミトンを外したため、拘束時間は約2時間であったことなどの事情の下では、本件抑制行為は患者が転倒、転落により重大な傷害を負う危険を避けるため緊急やむを得ず行われた行為であって、診療契約上の義務に違反するものではないと判断する。」というものでした。
最高裁のこの判決によって、現在の介護・医療水準と人員や設備、運営といった規程の中での身体拘束をめぐる法的判断が確定したといえます。
この最高裁判決で、特筆するところは、まず、そもそも身体拘束は必要やむを得ないと認められる場合にのみ許される、という前提を踏まえた上で、身体拘束が例外的に許される①「切迫性」、②「非代替性」、③「一時性」を入院していた高齢女性の実情から判断し、かつ、当該病院に入院する前の病院でも転倒し骨折していること、また、身体拘束があった日の10日程前にも転倒があったことなどをあげています。
ここ最近の特別養護老人ホームの裁判事例でも、誤嚥による度重なる急変に対しての対処の甘さから厳しい判断を下したもの(東京地裁平成19年5月28日判決)や、グループホームでの度重なる転倒転落による事故に対して、十分な措置を講じなかった点に大きなペナルティーを課したもの(大阪地裁平成19年11月7日判決)があります。
施設に入所している高齢者は、認知症や寝たきりのため、ほとんどの高齢者に何かがあった場合、大きな負傷につながることが事前に予想されることから、事故があった場合の次への対処方法や方策の取り方が争点になってきます。
今回のご質問や、最高裁が下した身体拘束についてのとらえ方についても、身体拘束が許されるための条件を正確に見極め、「適切な拘束」をする状況も今後、必然的に発生するものと思われます。その「適切な拘束」をするための見極めと解除のタイミング、そして同じ事故を何度も起こさないための取組みが大切ですね。
「どんな犬でも、一度は咬む」 アメリカの「ことわざ」です。
一度目は大目に見てくれますが、二度目は許されない、という意味だそうです。「先生、助けてください…」に対する答えです。「いつも助けてあげますよ。ただ、いつも精一杯の介護をしててください。その努力をどう挙証資料として表面化させるか。そのことを一緒になって考えていきますから…」
Q10. 私の施設では、記録の方法として「毎日のサービス実施」をチェックリストにして「○」「×」式のコメントをする方式を採っています。例えば、「皮膚のかぶれの軽減」に対しては、「○」…清拭しました。「スタッフ同士で日々のコミュニケーションをとっている」に対しては、「○」…申し送りの際に疑問点を聞きました。 このようなチェックリストによる記入方法で、記録の代用になるものなのか、教えてください。
A10. これまで、介護事故といえば、介護スタッフが利用者さんの介助中に誤って転倒・転落させてしまったり、また職員が見ていないところでの怪我であったり、と言うのが一般的でしたよね。
しかし、今後は利用者さん同士による事故が十分に考えられますし、その際の法人側(施設)の責任が問われてくるケースが多発するように思われます。これまでも利用者さん同士による事故がなかったわけではないんでしょうが、そこは両方の家族側が、当事者同士のことを「お互いにボケてるんだから、仕方がないですし、お互い様ですよ」と、害を加えた高齢者と害を被った高齢者、そして施設といった三者関係の修復は、被害にあった高齢者が死亡したりしない限りにおいては、穏便に解決されていた場合が多かったです。
しかし、死亡まではいかなくとも、入院等で医療費がかさんだり、今回のケースのようにショートの利用者さんが頚部骨折等で入院し、退院してからも在宅介護が難しくなり、施設入所しかないといった重症化した場合などは、今後の受け皿との関係で、両方の家族のストレスや欝憤が一気に施設に向けられることが多くなってくるものと思われます。
結論から言うと、今回のケースでは、法人側の入所者の管理についての適切な管理を行わなかった安全配慮義務違反の有無が問われることになると思われます。
両者に判断能力があるような場合の事件では、単純に傷害事件という形で処理できるのですが、認知症の高齢者同士の傷害事件となると、保育所や幼稚園での子ども同士の喧嘩で怪我をさせた・怪我をした場合と同様、成人か未成年かはともかくとして、責任を問えない者同士の争いとなりますから、争いのあった「場所」が主な責任主体としてクローズアップされるようになります。
この場合のリスクを考える上での前提条件として、加害者である入所者の認知症男性について、日常生活状況の把握が最も重要になってくると思われます。認知症の程度や暴言も含めた暴力行為の頻度、内容、時間帯、誘発させる要因に何らかのパターンがあるのか等です。
また、事故当時の介護スタッフの配置状況、関わり方も重要です。加害者である入所男性と、被害者であるシュート利用の高齢者が、施設内のどこの場所で接点があったのか? 加害者側の男性高齢者が自分の車椅子だと思い込み、被害者である高齢女性を突き飛ばす前に、おそらく何らかの事故を予見できる兆候があったと思われます。例えば、被害女性が乗っていた車椅子の取手の部分を揺さぶったであるだとか、また被害女性に大きな声で暴言があったであるだとか…。そのような事故を予見するような状況をスタッフが認識していたのか、と言う点については、事故発生時のその場、またはその場近くに、介護スタッフがどのような配置で一体何をしているところだったのかが争点になります。
さらに、介護スタッフが、事故の当事者同士の状況を予見できていたのであれば、次ぎにスタッフはどのような行為でトラブルを回避しようと試みたのか、が争点となります。たとえば、加害男性を自分の部屋、もしくはフロアに帰るように促したのか、逆に、被害女性を加害男性から遠ざけるために、違うフロアや階、部屋に移動させたのか、といった点です。
予見可能性と回避義務については、過失を構成する重要な要素ですからね。
そして最後に、事故発生後、加害者・被害者共の家族に誰がどう電話等で説明したのか、が問題となります。事故発生後どれくらいの時間が経過した時点で連絡をしたのか、連絡した際には、事実確認が十分にできた上での情報提供だったのか、その情報提供の際に、事故の当事者である被害者と加害者の二人の関係だけで発生したことを強調したのか、つまり当事者同士の関係だけを強調してしまった結果、どちらかの家族、もしくは両方の家族に、施設側(法人)が責任を転嫁しているかのような誤解を与える内容、もしくは伝え方になっていなかったか、などの点に注意しなければなりません。
はじめにもお伝えしましたとおり、法人側には、入所者の管理についての適切な管理を行わなかった安全配慮義務違反が問われることになります。その際、適切な管理の下、十分とは言えないまでも、当時の介護スタッフの人員、配置、彼らの判断や行動が、ある一定程度の安全を確保し、他の方法ではなく、選択した行為がより妥当であったということが第三者に説明でき、それを記録として文章化できるようにまでしておく発想が必要だと思います。
Q13. 私は管理栄養士です。私が勤務する特別養護老人ホームでは、食事の面に力を入れており、月一度のバイキング料理をはじめ、お正月の餅つき、鏡開きの際には餅の入ったぜんざいを提供しています。また高齢者の誕生日には、入所者から希望をうかがい、出前の寿司や鰻などをとって提供しています。利用者さんは非常に喜んでくれているのですが、いつか誤嚥事故につながり、せっかくお年寄りが楽しみにしているこのような行事が、リスクという視点から中止になってしまいそうで日々の業務もヒヤヒヤしながらこなしているといったところです。
高齢者の希望や嗜好を最大限取り入れたいという施設の思いは分かるのですが、高齢者のニーズは高まる一方です。
先生、食事の選定や、食事提供についてのリスクについて教えてください。
A13. 管理栄養士としての業務、お疲れ様です。施設の中での管理栄養士の役割については、今後ますます重要な位置づけになってくるように思われます。
食事についてのリスクとしては、一番に誤嚥が考えられますが、ユニット化や朝昼夜の食事提示における人員配置など、ハード面での制約や人員配置的な制度的制約か、法制度的には適合していたとしても、任意での改修や改善という点では、コストとのバランスで非常に難しい点があるのも理解しています。
施設においては、入所者の要介護度も上がり、認知症も重くなっている状況の中、食事を楽しみにしている利用者の方の意向をうかがいつつ、事故を起こさないようにしなければならない…。本当に難しいことと思っています。
最近の裁判事例の中で、食事中の誤嚥に関するものがありました。これは、特別養護老人ホームのなかで、入所者の誤嚥事故につき、介護職員に過失があるとしてその不法行為を認め、老人ホームの開設者の使用者責任が問われた事件です。
誤嚥となった食べ物は、玉子丼に入っていた鳴門かまぼこが喉に張りついて誤嚥を起こしたものです。この誤嚥に対して、口から泡を出していた段階で吸引の措置をしたのですが、その数分後再び利用者さんが口から泡を出して苦しそうな呼吸をしてチアノーゼが出ているのを職員が発見。再度吸引を試み、食事を一時中止し、その後介護職員らが車いすに乗った利用者を食堂から寮母室の前に運んで経過を見ていた際に、また利用者さんが顔面蒼白でぐったりとしている状況を発見した、という事例です。
裁判所は、「…これら度重なる急変に対して、医療の専門家である嘱託医に連絡して適切な処置を施し、119番通報をして救急車の出動を直ちに要請すべき義務を怠った」として施設側の過失を認定しました。
争点としては、玉子丼の鳴門かまぼこを誤嚥した点と、度重なる急変への対応の不十分さを問うものでした。
たしかに裁判所の言うことはそうかもしれませんが、人員配置上医師を常設する義務までない特別養護老人ホームにあって、医師への連絡や、また救急車の出動要請などについては、そのタイミングとその判断が非常に難しいのも事実としてあります。
この場合、考えられる食事中の誤嚥に関するリスクへの対応としては、誤嚥が疑われた場合の吸引の措置について、その処置が適切であったのかどうかをまず考えないといけません。現在、特別養護老人ホームにおいては介護スタッフが吸引器を使用した医療行為に関しても、しかるべき研修等を受けていれば違法性が阻却されるようになっています。この場合の誤嚥物の吸引が、どのような資格者が行った行為であるのかについては争点になっていませんが、初期対応のまずさを考えなければなりません。
そして誤飲となった異物を取り出したかどうかの確認、つまり誤嚥の原因となった異物が何であるのかを想定し、どこまでの吸引をすれば異物を取りきったとするのかについての判断が、度重なる急変とその対応に求められる視点です。また、今回のケースでは直接的な争点にはなっていませんが、誤嚥の原因となった玉子丼が、施設内で管理栄養士等によって提供されたものではなく、出前(外注)であったことも今後のリスクヘッジを考えるうえで重要なポイントになります。
誤解のないようにということですが、出前(外注)の食事提供が必ずしも悪いということではありません。施設では提供しにくいものもありますし、また個人の嗜好で自己負担ではあるもののどうしても○○が食べたい、といったニーズを叶えて差し上げるのもまた施設の役割だと思っています。しかし、その際、施設内での調理と食事提供であれば、利用者の方の咀嚼状況や病状等からの塩分調整といった配慮がアセスメントシートから分析でき、それが献立や食事の提供方法に反映させることも可能ですが、外注の場合、あくまでも健常者が食することを前提としている場合が圧倒的に多いものですから、出前についても、店側に食される利用者の状態を簡単にでも説明し、何らかの配慮が可能かどうかを確かめ、それでも提供できるかどうか、そして利用者ご本人に確認し、注文をとるという手続きが必要になります。もちろん、それらの経緯については記録しておかなくてはなりません。ケアする側の担当者が代わった場合でも、経緯の記録から手続きを踏襲することができますから。
食事は、高齢者施設にあって、入所者の方の最大の楽しみといっても過言ではない実態があるものの、喜んでいただく食事提供と誤嚥というリスクのはざまで、判断が難しいシーンもあろうかと思います。
食事や外出のリスクについても、具体的な例から考えたいと思います。誕生日には近くの大型スーパーの中に入っている回転寿司屋で、介護スタッフや家族も交えた外食の取り組みを実施している施設がありました。高齢者の方はたいそう喜び、「来年の誕生日もまた同じように寿司が食べたい」と施設に帰ってきてからも口にされるものですから、他の利用者の方も誕生日には外食をして喜んでいるということです。読者の皆さんは、一体何がこの場合でのリスクだと思われますか? リスクを最小限度に抑えるために、介護スタッフは事前に下見に行き、店側にどういった状況の高齢者が来店予定であるのか、また来店予定の高齢者の咀嚼状況等を簡単に説明したうえで、何らかの配慮が期待できるのか否かについても聞き取りを行い、そのやり取りを記録しておく必要があります。
これらの「下見」は、何も外食だけに限らず、これから暖かくなった際に、桜見物などの外出も施設行事として組み入れられていると思いますが、その際にも天候などの関係で地面が滑りやすくなっていないか、他の見物客との往来も想定した場所の確保と、より適した時間帯の設定等が必要になります。外出当日に何らかの事故が起こった場合でも、下見に行き、その時には想定できなかった事態であることを証明することが、過失責任割合との関係でも免責の部分で重要になってきます。
これまでは、施設ケアマネの方からであったり、また生活相談員の方からのご質問がほとんどを占めていましたが、管理栄養士の方からのご質問、ありがたく思っています。施設の中での栄養士の役割は、今後ますますクローズアップされるでしょうし、利用者の方の「美味しかったよ」という笑顔をはじめとして目に見える形でのやりがいを得られる職種です。リスクを一方で考えながらも最高の食事を皆さんに提供してくださいね。
Q16. 先生に質問ですが、高齢者施設内での転倒・転落や誤嚥の事故で、実際に裁判で勝ったケースはあるのでしょうか?先生のお話では、施設内で事故が起こった場合、記録の不備や職員の未熟さから、圧倒的に利用者や家族側に有利な条件(法人側には不利)ばかりがあるように思います。
実際に裁判にまで到ったケースで施設側が勝ったような事例から、何に注意をして部下を指導し、事故が起こらない仕組みをどう作ればいいのか、といつも悩んでいます。
A16. そうですね。皆さんの業務の中身をみると、躓いて転べば大腿骨の頸部骨折につながり、食事をすれば誤嚥による窒息死に到るような方ばかりをお世話しているわけですから、対照的に保育所や幼稚園での子どもに同じような状況が発生したとしても、大けがやまた亡くなるようなことはなく、注意義務のかけかたや過失のとらえ方も随分と違うものがありますよね。
介護事故をめぐる多くの家族(遺族)の主張を聞いても、「そもそも高齢者が転んだら、こうなることは…」「そもそもお年寄りの食事中に少しでも目を離すなんて…」という圧倒的に「ごもっとも」な主張で向かってくるわけです。心の中では、「なら、家族で見てても同じようなことが起こりますよ…」と言いたいところですが、そうとも言えず、「私たちはお金も払ってて、あなたたちは介護のプロなんでしょ…!!!」とくるものですから、もう何も反論できなくなるわけです。あげくの果てには、「おじいちゃんを返して…!!!あんなにも好きだったのに…。この人殺し…」とくれば、もう話し合いでは解決せず、裁判になってしまうわけですよね。
法人側にとっても、変に和解や示談でことを済ませるより、裁判でスタッフの介護行為の正当性を主張し、職員や組織を守る展開が、今後の法人づくりの上でも良い場合もあります。
介護事故が裁判にまで発展したケースでいえば、ご質問の通り、法人が負けてしまうケースがほとんどです。下記に、最近の高齢者施設での誤嚥事故で法人側が勝ったケースを紹介しますが、裁判の勝ち負けは担当した弁護士が介護現場の実態や介護事故が医療事故と微妙に異なることが分かっているのか、といった専門家としての力量にも左右されますし、また両方の意見を聞く裁判官の得手不得手にも左右されるのが事実です。
逆に裁判で勝ちを収めた事例から、「こういう点を主張すれば、はたして勝てたのか…?」という疑問をぶつけながら質問にお答えしたいと思います。
当時82歳の女性が、高齢者施設に入所し3か月目の夕食時に誤嚥、死亡した事件ですが、利用者である高齢女性の死因と施設及び介護スタッフらの過失が争点になったものです(平成22年8月26日横浜地裁棄却<確定>)。
この事例では、遺族である高齢女性の夫と彼らの長男長女が原告として登場し、また誤嚥直後の様子を同じ入所者である認知症の利用者の証言が出されるなどした事件でした。
争点の一つである死因については、夕食時に食事を詰まらせたことによる誤嚥なのか、それとも利用者の持病であった心筋梗塞または脳梗塞によって意識がなくなり、それに伴って吐き戻しの誤嚥を原因とするものなのかが問われました。
判決では結論として食物の誤嚥ではなく、既往症から考えて脳梗塞もしくは心筋梗塞による発作からの吐き戻しによる窒息死と判断しています。しかし、判決文をみると、施設に入所中、心疾患および脳疾患に関する投薬はなく、また脳梗塞や心筋梗塞の発症を抑制するための対応もとられていないこと、さらに裁判所は食事による誤嚥ではないことの理由として、「…仮に食物を誤嚥し、窒息して意識消失に至ったのであれば、当人は苦しんだり、むせ込んだり、胸を叩いたりするなどの動作をしたり、音を立てたりするのが自然な成り行きと考えられるところ、当人にこのような動作をしたことを認めるに足る証拠はない…」という判断をしています。しかし誤嚥というのは、むせない誤嚥も実際の介護事故では多く、過去にもむせない誤嚥を経験したことがないヘルパーが誤嚥であることを気づかずに救急対応が遅れ裁判になったケースも存在します。このようなことから、死因についてはかなりの疑問が残るところです。
二つ目の争点である施設ならび介護スタッフの過失については、誤嚥等の緊急時における職員教育、食事介助中の介助者の立ち位置、見守りを含めた観察、誤嚥後の救命措置の方法などが細かく問われました。
ここでも判決では、施設ないし介護スタッフの働き方からみた過失について、「職員教育」では救急救命マニュアルの作成、急変時にとるべき内容及び方法、医師及び看護師への連絡、コールの手順、救急搬送の手順書が存在し、年一回の定期的な勉強会の実施等から、スタッフ教育が不十分であるとまでは評価できない、という認識をしました。ですが、これらの手順書やマニュアルがいつ頃つくられたもので、事故当時でも有効なものであるのか、また研修の内容、頻度、到達度等、効果測定なるものがあるのか、といった研修や教育の有効性が問われるべきだったと思います。つまり年一回の勉強会で足りる知識・技能であったものなのか、参加者は全員なのか、という視点です。
また、「適切な人員配置」についても、裁判所が言う通り、事故当時の当施設において基準省令上の人員基準は満たしており、この部分では問題はないように思われます。しかし、人員の基準ではなく、たとえ利用者との割合で人員基準は満たしていた場合でも、「ヒヤリハッと報告書」などから、時間帯また繁忙時間における職員配置に無理がなかったのか、報告書からも職員配置が手薄な場面での事故が頻発していたのではないか、といった視点が今後の争点となってもおかしくはないと思います。
次に「入所者を適切な位置で食事をさせ、注意深く観察することの義務」についても、介護士が突然の意識消失を予見することができず、観察の程度も不十分ではなく、席替えをしなかった点について過失はない、と裁判所は判断しました。しかし利用者のアセスメントから、脳梗塞や心筋梗塞などの持病は把握できるはずですし、また事故がおきた一週間程度前から5回の嘔吐の事実を認識していながら、見守り等も含めた食事中の誤嚥を予見できなかったとはいえないように思います。
最後に、介護施設における裁判事例もかなりの数にのぼり、過失責任を問う上でも争点の項目が多様化しているように思います。たとえば、「AEDの設置義務」や「適切な救命措置をとらなかった過失」についても争点になりましたが、高齢者施設にAEDの設置義務がないこと、またエアウェイ挿入や吸引の行為は法令上禁止されている医行為に該当する可能性が極めて高いため使用しなかったことに対しての違法性はないと判断されています。さらに、アンビューバッグの使用や、心臓マッサージの実施、痰切り用(吸引器用)カテーテルの使用や掃除機用カテーテルの使用といった細かい項目についても、今後、誤嚥事故等での介護職員・法人に求められる緊急時の対応方法に示唆するものがあると思われます。
ただ、ご質問にあるように、「何に注意をして部下を指導し、事故が起こらない仕組みをどう作ればいいのか」については、「ヒヤリ・ハッと報告書」や「事故報告書」を手かがりに、細かな検証作業が必要です。具体的には、「記録の整合性」です。
つまり、アセスメントからケアプランへの落とし込み、そして長期・短期目標を記載した介護計画から実際に提供された介護記録への落とし込みへの振り返りを行うことで、「記録として何を書く必要があり、どんな文言が不要なのか」といった考察が、必要とされる情報収集の項目を明らかにし、同じ事故を繰り返さない要素になりますから。
具体的な例をあげると、「転倒に注意しながら安定した歩行」とケアプラン上に長期・短期目標としてあげながら、歩行・補助具の活用等の記録がまったくなく、転倒に配慮した記録が一切なかったり、またケアプランの長期・短期目標に「違和感なく食べるものの、今後、咀嚼しやすい献立」としながら、実際の実施記録には「食事の際のむせ込みが多く続く」というような、逆のことが記録化されているなど、矛盾する整合性のない記載がある記録を多く目にします。言い換えると、転倒や誤嚥については、長期・短期目標にそれらの注意事項があげられていながら、実施記録の方では些細な表現のなかにプランや目標とまったく逆のことが記載されたような記録が目につくということです。
「記録を読んで、どんなケアプランなのかが想像できるか?」、「ケアプランをみて、どんなアセスメントなのかが想像できるか?つまり、利用者像がイメージできるか?」といった逆の視点から、「限られた時間や交渉のなかで何を聞いておかなければいけないのか」「何をケアプラン上の目標としてあげるべきなのか」。そして「実際の介護サービスを提供していくうえで、現実可能なものであるのか」という視点を養っておくことで、裁判の勝敗はともかくとして、介護スタッフが実践している行為の正当性が裏づけられますから。
Q18. 特別養護老人ホームで事務長をしているものです。烏野先生の連載を読ませて頂き、いつも目からウロコが落ちる思いなのですが、考えれば考えるほど、「介護事故って何…?」というそもそも論が頭をよぎって、よぎるだけではなく、頭から離れられなくなっています。
介護スタッフ向けの法人内研修を企画しなければならない立場にあるのですが、病院の事務に長く携わってきた私ですので、病院での医療事故と介護施設での介護事故の違いがよく分かりません。
また連載の中でもありましたが、過失責任との関係で、「ヒヤリ・ハッと」の分析が欠かせないことは理解しているんですが、何をもって事故と数える「アクシデント」で、何が「インシデント」にあたるのか…。
そもそも介護事故とは何なのか…、混乱してきております。
A18. 事務長様からのメールでありがたく思っております。最近、私の方で頂戴するメールが、現場の介護スタッフ以上に、管理者や事務長様、また施設長様からのものが非常に多くみられる傾向にあります。
ご質問が多岐にわたっていますが、順を追って説明させて頂きますね。
まず、「介護事故…」と聞くと、介護現場で働くスタッフのみならず管理者の皆さまも、すぐさま「転倒・転落」「誤嚥」「薬の誤配」などが頭をよぎるでしょう。介護事故の実態という意味では、先ほどの「転倒・転落」「誤嚥」「薬の誤配」「溺水」などをイメージしますが、厳密に「介護事故とは…?」という介護事故の定義について、いまだはっきりとしたものは存在しません。
国も、数年前に介護事故の定義も含めた実態把握のための調査に乗り出しましたが、「何をもって介護事故とするのか?」、「『ヒヤリ・ハッと』でいうインシデントと一体何が異なるのか?」という疑問に対する考え方が、各都道府県によってあまりにも違うものですから、調査を断念した経緯があります。
しかし、介護事故そのものの定義などがいまだ不確定であったとしても、介護保険制度の誕生によって契約の当事者性が高まったことを受け、保険契約との考え方にもとづき、介護中での事故に対して責任の所在が問われ、賠償のあり方についても論議されるようになった頃から、介護業界ではリスクマネジメントという発想が定着するようになってきました。
つまり、介護保険制度の取り扱い事業所にとっては、介護サービスの提供業務が民法上での契約関係におかれることから、介助中の事故が発生した場合、その損害の補償については第一次的にサービス提供者である事業所がその責を負うと言うルールが確立したわけです。
その結果、介護事故をめぐっての争いが避けられず、裁判にまで到るケースが多く現れることになります。
介護事故の特徴を、介護事故裁判の特徴と置き換えて話を進めた方が、争点が明確になるものですから、以下に介護事故裁判の特徴を説明したいと思います。
介護事故における裁判は、医療における事故とのそれと比較した場合、検証が非常に難しい点が特徴的です。医療事故における検証作業では、まず期間が定められた治療という目標、言い換えるならゴールが明確ですから、その疾病やけがに対して、どのような経過でどんな施術が、また何の薬剤の投与が必要か、という流れがある意味では合理的に決まっているわけです。つまり、ある一定程度においてマニュアル化が可能なわけです。
しかし介護事故の場合、自立した生活を支援するということが目的となりますので、ほとんどの場合で継続性が主となる日常生活上の世話に力点が置かれることになります。
医療との比較で考えてみても、介護が食事、排泄、入浴、就寝といった日常生活上の世話の過程で事故が起こるものですから、家族ではない職業専門職の者が実施する際の専門家たる行為についての論議も、医療関係者のそれよりも遅れているというのが実情です。ですから、「誰の指示で、どこまでの介護をすればいいのか?」という点で、介護スタッフだけではなく、指導する立場にある管理者の方も、相談を頂いた事務長様同様に悩んでいることだと思います。
また、「どこまで介護をすればいいのか…」、といった介護行為そのものをめぐる専門性の不確定性に加え、高齢者層の劇的な変化という視点も、介護事故をクローズアップさせる要素の一つです。
最近の介護事故裁判をめぐる傾向を鳥瞰しても、今の高齢化を反映したものとなっており、「保護の対象としての高齢者」ではなく、「権利の対象=消費者としての高齢者」の像が浮かび上がります。つまり現在、介護サービスを利用している者が、70~100歳といったいわゆる戦争経験者である層から、今後、団塊世代をはじめとしたシニアといわれる介護予備軍の出現が、介護サービスを提供する際のリスクという点で拍車をかけている傾向も否めません。かつ、高齢者の層の変化だけではなく、介護現場で働くスタッフにも変化が現れてきています。介護事故の当事者という意味で、利用者や家族が、施設なり事業所である法人を訴えるという従来のパターンだけではなく、認知症の利用者が認知症の利用者に害を与えて訴える(遺族や家族も含む)ケースや、また最近では介護スタッフが利用者や家族を訴える(実際には判断能力のない利用者の加害行為であることから、彼らの責任能力を問えないため、結果として管理者である法人が職員から訴えられることになる)ケースまで、介護事故の際における当事者とそのベクトルに変化がみられます。
このようなことから、数量的にも介護事故は増加していると実感として思われますが、介護事故の定義がいまだ確立しておらず、当事者も含めた問題の現れ方も多様化していることから、統計的な把握は難しいのが実情となっています。
一昔前であれば、利用者や家族も「世話になっている」という意識から、法人に対して法廷での争いなど想像もつかなかったことでしょう。しかし、現在、介護労働の提供が民法上の契約として位置づけられ、かつ利用者負担が強化される中、当然のこととして「サービスとしての介護」をめぐって、争いが多発するのも理解できます。
利用者や家族の意向に沿って、また彼らの望む通りの介護を行っていれば、それが「いい介護」につながるのでしょうか? そうではないはずです。
介護保険法の目的や趣旨にもある「自立支援」を考えた際、「利用者のできることはご本人で行ってもらう」という介護が、時として「前の職員はここまでやってくれたのに…」と利用者やその家族からなじられる場合もあろうかと思います。
「利用者や家族が望む介護」ではなく、介護のプロとしてどこまでの介護が業務上の責務なのか、ということを介護事故の裁判事例から浮かび上がる項目や、その項目に対する判断を素材に、日々の介護業務のあり方を問い続ける習慣が必要であるように思います。
つまり、介護事故を分析すると言うことは、皆さんが日々の介護業務をどう高めたいと目標を掲げながら挑戦しておられるのか、何を見直す・改善の余地が残っているのか、を問う作業であるとお考え下さい。
Q21. 特別養護老人ホームで副施設長を仰せつかっている者です。烏野先生の連載は、いつも楽しみに読ませて頂いておりますし、その月の法人内研修はいつも先生の連載テーマを活用させて頂いております。
さて、日々の業務を振り返ってみると、最近特に利用者や家族からのクレームが多く、転倒などの事故がある度に家族はこれ見よがしに「どうしてくれるんだ…!!」とものすごい剣幕で迫ってこられます。
骨折で入院をした場合など、「治療費はすべて施設が負担し、退院してからの入所にかかる費用は本人が死ぬまで施設の負担…!!」とおっしゃる家族の方など…。このような状況ですから、介護スタッフも転倒・転落や誤嚥の恐れのあるリスキーなお年寄りなどの担当をできれば避けたいという思いが強く、また管理者である我々も利用者になるであろう方の家族をよく見て、クレーマーになりそうな家族は初めからサービスを断ろうか…、と思ってしまう衝動に駆られております。
これまでの連載の中でも利用者さんに対してどのような責任があるのかについては理解しましたが、具体的に「施設の責任」と「スタッフの責任」について教えて頂ければと思い、お手紙をしたためました。
A21. いつもは生活相談員や施設ケアマネ、介護スタッフからのメールを整理し、そのひと月間でもっとも多いご相談に応えるというやり方で一年以上、連載を続けてまいりました。この度は、ご丁寧なお手紙を頂戴しました関係で、先回お約束をしていた「どうやって介護現場で残業を管理すればいいのか…?」についてのお話しは次回にしたいと思っております。ごめんなさい。
そうですね。私の方にも、一日1?2件のペースで「施設内で転倒(誤嚥)させてしまい、家族が法的な解決も考えていると言われているのですが…」という非常に切迫した質問があります。
また、「これ見よがしに…」事故にかこつけて利用料の支払いを渋る家族や、私の経験でも、一度弁護士を入れたり、提訴したものの和解で解決を図った家族は、また違う施設で同じようなトラブルで裁判を起こして多額の金銭を要求するケースもあります。「味をしめた」とでもいいましょうか。
最近、介護報酬の不正請求事件で指定の廃止をめぐる報道が多くありますが、「介護を喰いモノにする」事業所の増加によって、利用者や家族の権利を守らないといけないと思う一方で、些細なことで無理難題をふっかけてくる家族の横暴にも、落とし所を見つけられないまま介護事業所を責め立てても、最後にはクレーマー自身が自分で自分の首を絞める結果になってしまうのに、と思ってしまう瞬間もあります。
さて、介護事故などの場合において、「介護事業所として、利用者といかなる契約関係にあり、何を約束として守らなければならないのか…」につきましては、これまでの連載でも触れてきたところですが、もう少し詳しく「法人としての責任」と、「介護スタッフ個人の責任」について、というご質問でしたね。
たしかに、ご相談のように、一度介護事故が起こり裁判にまで発展しそうな時というのは、事故を起こしてしまった当事者である介護スタッフのストレスや不安は相当なものになります。ですがそれ以上に、管理者が対応を一歩間違えると、事故を起こしてしまった介護スタッフが責任を感じ辞表願いを出すなど、それでなくとも人材不足に頭を悩ませる事業所においては、事故そのものよりも人材の流出による被害は計り知れない事態となります。
また介護の仕事とは、介護スタッフ個人の働き方やキャラクターが日常業務に派生しやすい性格を持っていることから、事故が起こった場合など「自分のせいで…」という感覚に陥りやすい傾向もうかがえます。そして、リスクマネジメントという視点を見誤ると事故が起きやすいリスキーな高齢者に対して、「担当したくない…、受け持ちたくない…」という誤った発想に陥る可能性も否定できません。
「法人としての責任」でいうと、現在の介護保険法のもとでは、事業所である法人と利用者との間に利用契約が締結され、提供される介護サービスが対価性のあるものとして位置づけられることから、とりわけ事業所の管理者や介護スタッフである履行補助者の責任がより明確なものになりました。
事業所と利用者との法的関係は、法人と利用者との間で締結されるサービス利用契約に基づく契約関係となります。この場合のサービス利用契約とは、法人と利用者の双方が契約上の債務を負っているということを意味します。事業所は利用者に対して設備の利用やまた居室の使用、そして利用契約の内容に盛込まれた必要な介護サービスを提供する債務を負い、一方の利用者は事業所に対してサービス利用への対価として、介護報酬に基づく利用者負担金などを支払う債務を負うことになります。
そして、実際には事業所のスタッフである介護従事者が、事業所の履行補助者として利用者にサービスを提供することから、事故などが起こった場合、介護スタッフに対する過失の有無が問題となります。
では、次に「介護スタッフ個人の責任」とは、どの程度のものなんでしょうか?介護スタッフは、利用者との間で直接的な契約関係にはなく、サービスを提供する側から見た場合、法人のトップが契約書に名前と印鑑を押し、利用者と契約をする形式をとっています。つまり、社会福祉法人や医療法人等であれば理事長ですし、株式会社であれば代表取締役社長が契約の当事者になります。
ですが、理事長や社長が直接利用者に介護サービスを提供するわけではなく、実際には介護スタッフが理事長や社長の履行補助者という位置づけでサービスを提供することになります。皆さんが行っている日々の業務は、あくまでも理事長や社長の代行的な補助行為と言うことになります。
では、理事長や社長の代わりに働く介護スタッフとは、正社員でなければならないのでしょうか?
代わりに介護を補助するスタッフは、正規(常勤)の職員という意味だけではなく、例えボランティアによる無償の奉仕活動であったとしても責任自体の存否には関係しません。つまりボランティアであったとしても、事業所の正職員に課せられるほどの高い注意義務までは求められないにせよ、「善良なる管理者の注意義務」(略称「善管注意義務」民法第400条)を負うものと考えられます。この場合の注意義務とは、行為者の能力に応じた注意義務ではなく、その行為者の属する職業や社会的地位に応じて期待される一定水準の注意義務を指すと考えられています。
言い換えれば、皆さんがいま持っている資格で仕事をしている以上、「新人でまだキャリアが浅いから…」といった理由で責任が軽くなるというわけではないということです。利用者や家族にとってみれば、男性であろうと女性であろうと、また若かろうとベテランであろうと、皆さんが手渡した名刺の肩書き(ステイタス)で、その業界の専門性や立場を判断するんですからね。
介護スタッフ個人に求められる責任の方が強いように思われるかもしれませんが、たとえ履行補助者である介護スタッフの過失によって事故を招いた場合であったとしても、利用者と介護スタッフとの間には直接的な契約関係にないものですから、個人が契約に基づく債務不履行を問われることはなく、契約当事者である法人トップの責任と考えて下さい。しかし、虐待など明らかに介護スタッフによる過失で事故が起った場合には、不法行為責任により介護スタッフの賠償責任が問われると同時に、職員の監督上の責任者である法人のトップが、使用者責任を負うことになります。
つまり、実際に介護を行う皆さんには、それぞれプロとしての役割と責任が求められますが、皆さんはサービス提供上、契約当事者である法人トップの代わりとして仕事をしているに過ぎず、かりに皆さんに大きく非があるような事故が生じたとしても、皆さんを雇用している法人のトップが、使用者としての全責任を負うという関係になっています。
Q32. いつも、先生の連載を月ごとの施設内研修で利用させて頂いています。
東海地方の特養に勤務する生活相談員です。烏野先生がおっしゃる通り、大災害に備えたリスク分析をしなければならないのですが、日常的に小さな介護事故が多く発生し、「ヒヤリ・ハッと報告書」や「事故報告書」、それへの対応で追われている毎日です。利用者家族からの期待も大きいなか、どうすれば介護事故をなくすことができるんでしょうか?
A32. 「日々の業務、本当にお疲れ様です。皆さんの努力で、高齢者の生活が保たれていることに、深く敬意を表したいと思います。
ご質問の件ですが、「どうすれば、介護事故をなくすことができるのか…」。
その方法はありません。
介護現場では、必ず事故が起こる、と考えて下さい。事故が起こるということを前提に、「起こさないための取組みと」と、「起こしてからの対応のあり方」が重要だ
と思って下さい。
くどいようですが、事故は必ず起こるものですから。「介護事故、ゼロ」と、「オムツ、ゼロ」とはわけが違うんです。
介護事故の法的な分析につきましては、過去のご質問で答えておりますから、それを参考にして頂きたいと思いますが、少なくとも事故をなくすという視点からではなく、
「事故にどう向き合うのか」という観点から話しを進めたいと思っています。
最近の高齢者施設で起こった転倒事故の裁判から考えていきましょう。
この事例は、事故当時78歳で、骨粗鬆症、パーキンソン病(重症度分類が4)、高血圧症、神経症、抑うつ状態、めまい、そして軽度の認知症等の既往歴のある高齢者が、早朝に転倒していたと思われる事例です(平成24年3月28日東京地方裁判所一部認容・一部棄却で控訴)。
「早朝に転倒していたと思われる」と言いましたのは、早朝に介護士が車いすで原告をトイレ誘導した際、自力でトイレブース内の手すりを使って車いすから便座まで
移動しての排尿時、「私、転んじゃったの」という利用者の発言から明らかになったものです。
ここで紹介する主な争点は、転倒回避義務違反に係る債務不履行ですが、それよりもその背景に何があるのかを探っていきましょう。
利用者の家族側は転倒の回避義務違反について、
1、転倒しないよう介助することができるよう、職員らが十分に見守りできる場所に原告のベッドを置き、適切に見守りをする義務。
2、排泄介助を工夫する義務。
3、職員が随時応援に入れるような柔軟な勤務体制にする義務。
4、日常的に適切な歩行訓練をする義務。
5、転倒を防ぐため、ベッドの高さの低くする義務。
6、側面に手すりを設置する義務。
7、転倒時の骨折を防ぐために弾力のある床材を使用する義務。
を主張していました。
高齢者施設では、とりわけ「転倒事故」が最も多く発生するものですから、皆さんの施設でもこのようなトラブルがあった際、以上のような点で家族からのクレームに対
応しなければならないということです。
私がとても気になった点としては、上記の5「転倒を防ぐため、ベッドの高さの低くする義務」と、7「転倒時の骨折を防ぐために弾力のある床材を使用する義務」についてです。施設側は、5について「利用者がベッドに座った際、足が床に届く位置に設定し、もっとも立ち上がりやすい高さになっている」と主張しました。
7については、「弾力のある床材にしてしまうと、車椅子での移動やベッドの移動がしづらくなり、利用者にとっても歩きづらく転倒しやすくなってしまう」と抗弁しました。たしかに利用者の歩行を安定させる取り組みとしては、模範的な答えであると思いましたが、介護記録によると、「平成20年6月5日…夜中に転倒したと話す。ポータブルトイレの蓋を取ろうとしてよろけて転ぶとのこと。」、「平成21年1月12日…シルバーカーを引いて後ろ向きに歩いていたら後ろ向きに転倒したとのこと。」、「平成21年4月8日…居室中央で倒れている。
同室者によると、トイレに行こうとしてシルバーカーごと倒れたとのこと。」と、約1年間の記録の中にほぼ毎月2〜3回程度の転倒記録があるわけです。
その表現も、「—のこと」というように、直接の転倒を見たわけではない、聞き取ったような状況が伺えるわけです。
施設内での転倒事故の場合、職員による介助中に転倒させてしまったというよりはむしろ、「いつの間にか転倒していた」というように、転倒から時間が経過した後に転んでいることを発見するようなことは非常に多いと思います。当然のことながら、介護保険法上でも施設であれば3対1の職員人員の配置基準ですから、マンツーマンでの介護ではないので、観察に不十分なところがあるのも致し方ない点です。
また、ひと月の間に何度も同じような転倒を繰り返し、スタッフもそれなりの対応を会議等で確認するものの、決定的な解決策が見当たらないまま、「見守り」を続ける場合もあろうかと思います。
ですが、今回のケースの場合、「利用者がベッドに座った際、足が床に届く位置に設定し、もっとも立ち上がりやすい高さになっている」であるだとか、「弾力のある床材にしてしまうと、車椅子での移動やベッドの移動がしづらくなり、利用者にとっても歩きづらく転倒しやすくなってしまう」という、立ち上がりやすく歩行を容易にするという、一見正論のように見える主張も、一年間を通じて同じような発見できなかった転倒が十数回みられるということは、歩く条件を整えながらも放置しているような環境から、施設側の主張に後付けのような言い訳にしか思えないような抗弁が繰り返されているわけです。
介護事故のリスクを最大限少なくすることは可能です。先ほどの事例のような転倒のおそれのある利用者の場合、部屋の中心に畳を敷き、そこでベッドではなく布団にすれば、完全に立ち上がれないものですから転倒のリスクは極端に減少できます。誤嚥のおそれのある利用者に対しては、胃瘻造設することで誤嚥する危険性は激少します。ですが、それはもう介護ではなくなるわけです。
介護事故のリスクマネジメントとは、事故を完全になくすことではなく、「どこまでのリスクを背負うのか」という視点が必要です。歩行訓練をすれば転倒骨折のリスクはつきまといます。経口摂取することで食事の喜びを与えようとすれば、誤嚥による窒息のリスクはあります。
ではどちらの選択を支持するのか? 完全にリスクを取り去る非人間的な介護と、リスクを抱えながらもそのリスクを前提とした介護と。答えは、法人の理念を再度確認してみて下さい。施設であれば玄関等に大きく掲げてあるはずです。その理念に照らし合わせた場合、どちらの介護を行うのか、迷った時には法人の理念に立ち返って下さい。
もともと高齢者施設に入所されるような要介護者は、リスクの塊のようなものです。そのリスクとどう付き合うのか、どこまでのリスクを良しとするのか、それを職員全員で合意することが、いまできる最大のリスクマネジメントなんですよ。
Q38.
からすの先生、いつも連載を楽しみにしております。九州地方の特別養護老人ホームで生活相談員をしている者です。先日、お昼ご飯の最中に、誤嚥の事故が起こりました。幸い、利用者が死亡に到るようなことにはならず、周りのスタッフによる迅速な判断と処置とで事無きを得ました。
ですが、介護スタッフは事故当時、利用者の口にタイミングよく食事を運び、喉を注視しながら飲み込むまでの確認も怠っていませんでした。しかし、むせない誤嚥だったようで、「気づくのが一歩遅ければ…」と思うと、まだ研修中である新人が大量に入社してくる四月以降、不安でいっぱいになります。
とくに、ご家族にも状況だけはお話ししましたが、「二度とこのようなことが起こらないようにして欲しい」と釘を刺され、介護スタッフにもリスクのある利用者への介助に委縮しているようなところも見られます。
介護事故の考え方やとらえ方について、教えて頂きたいのですが。
A38. 生活相談員としての日々の業務、本当にお疲れ様です。介護事故が起こった際の連絡等については、生活相談員の役目だと思いますから、さぞかし家族への対応に気を遣われたと思います。
介護事故については、これまでも具体的な事例を中心に、その争点から皆さんに考えて頂ける素材を提供してきたかと思いますが、今回は、もう少し大きく介護事故そのものについて解説したいと思います。
そもそも「介護事故」については、転倒・転落や誤嚥といった現象そのものについてのイメージははっきりとしているものの、介護事故の定義となると、いまだに確立されたものはありません。言葉のニュアンスによるものでもあるのですが、「介護事故」の介護というのが、高齢者のみならず障がい者や子どもに対してのケアまで含みこんでしまうという点や、また「介護事故」の事故という考え方も、医療過誤などと比較した場合、医療過誤のように積極的な行為について誤りがあった、つまり、ある特定の不適切な行為を行ったことによる損害というよりは、むしろ介護事故の場合には、「何もしなかった」ことによる損害の発生が問題になるわけです。「うっかり、目を離したすきに…」という具合です。
介護現場で起きる事故というものは、高齢者施設のように彼らに生活の場を提供し、その場の管理を任されている責任の下で発生する点に特徴があるものですから、「気づかなかった」、「誰も見ていなかった」という不作為が、争点になってしまうという性格を持っています。
ただ、そうなりますと、介護サービスを利用する段階で、転倒・転落や誤嚥のリスクが非常に大きい高齢者を預かるわけですから、無限大に責任があるように思われるかもしれません。しかし、高齢者自身の責任(過失)を問う裁判事例も少なくはありません。たとえば、59歳の障がい者に対する歩行介助が争点になったケースでは、「(原告は)おそらく少しくらいなら大丈夫との判断に基づいて歩き始めたものと思われるが、結局、本件事故は、判断を誤って介護者なしで歩き始めた原告自身の過失によって生じたものといわざるを得ず…」(東京地裁平成10年7月28日判決)という判決や、また85歳の高齢者が区立の保養所の段差によって転倒し骨折したケースでも、「原告は、高齢者が急いで降りることは危険であることを十分認識していたものと認められる。…原告の側にも、踏み台のある洋室側から降りないで、踏み台のない通路側から急いで降りた点に相当の過失がある。」(東京地裁平成13年5月11日判決)として、原告側に6割の過失を認めたものもあるわけです。
ただし、以上のようなケースでは、認知症等がなく、判断能力が十分にある高齢者に対しての過失責任を問うものですが、高齢者施設での利用者の場合、ほとんどが認知症等で判断能力の乏しい利用者が相手となるため、一般的な市民法的感覚が通用しないということになってしまいます。ですから、介護事故の防止と、認知症ケアの充実とは車の両輪のように同時並行での研鑽が必要になるということです。
デイサービスやショートステイといった介護保険法上では在宅サービスに位置づけられているようなサービスであっても、要介護高齢者の身柄を預かっている場でのサービス提供中の事故という意味では、責任の重さはさておき、責任の有無については有ると言わざるを得ないのが実情です。過去の裁判事例から判断しても、転倒・転落や誤嚥と死亡との因果関係が明確ではなくとも慰謝料という名目で、損害額が認定されているケースが多くみられます。因果関係が十分に確定されなくても、「預かっていた」というだけで場を提供した施設や法人側に非があると言われれば、預かった側としてはたまったものではありません。
最近の厚生労働省『人口動態統計』からみた「不慮の事故死亡統計」では、誤嚥等の窒息でみると、高齢者施設での窒息死の6倍以上が自宅での窒息死となっていますし、転倒・転落でみると自宅での死亡事故は高齢者施設の約10倍近い数字となっています。ということは、専門職である介護スタッフの努力によってこれらの死亡事故を未然に防いでいる実態も存在するわけです。介護サービス利用時に、家族に対してこのような実態をお話しするかどうかまではともかくとして、高齢となり生物体としての機能が低下してきているような場合、ご相談にもあったように、いくら十分な見守りを実施していたとしても、避けられない現象が発生するわけです。
なかでも、高齢者施設で多発する介護事故については、転倒・転落が最も多く、ついで誤嚥となりますが、この二つには明らかな違いがあります。誤嚥事故の場合には、ある意味でall-or-nothing(オールオアナッシング)なところがあり、誤嚥が発生しても蘇生や適切な処置によって回復したとすれば、事故が起こる前の状態に戻れるわけです。さもなくば死亡か。また、食事が喉に詰まった場合の窒息と、食事中に心不全や心筋梗塞等が発症し吐き戻っての窒息とは、過失割合が異なるようにも思います。なので、十分な見守りをし続けていたにもかかわらず、事故を防ぎきれなかったということは起こり得るわけです。しかし、転倒・転落の場合には、最悪死亡に到らなくとも、大腿部の頸部骨折や圧迫骨折の結果、要介護度が上がるなど、より重度化するケースがほとんどなものですから、転倒・転落の恐れのある高齢者には、たえず見守る必要が施設や法人側にはあるということなんです。ですから、ヒヤリ・ハッと等の分析の仕方も、誤嚥事故と転倒・転落事故とでは違った論議が必要ということなんです。
以前の連載にも載せましたが、介護事故をゼロにすることは無理です。事故は必ず起こるものと認識してください。そのうえで、どこまでのリスクを負えるのか、どこまでが現在の施設のハード面、またマンパワーで対応できることなのかを、精神論だけではなく考え続ける視点が必要となります。
Q48. 特別養護老人ホームに併設しているデイサービスで、管理者をしている者です。いつも先生の連載を読みながら、どこまでが施設(法人)としての責任であり、またどこまでを家族にお願いしてもいいのか、分からなくなることがあります。たとえば、デイを利用されている時に、道を隔てた神社にお参りに行きたい、であるだとか、それほど遠くではないものの先祖のお墓に手をあわせに行きたい、であるだとか…。もちろん、その程度のことであれば、一緒に同行しお付き合いするんですが、「もし、ここで利用者さんが転倒でもしたら、いったい誰の責任になるんだろうか?」と、一緒にお付き合いする行為に戸惑うことがしばしばあります。先生、何かいいアドバイスを下さい。
A48. いつも連載を読んで頂き、ありがとうございます。皆さんのスキルアップになることを考えながら、毎月書かせて頂いております。利用者さんが望まれることを行い、無事に帰ってくることができれば、高齢者にとっては思いが満たされ、皆さんにとっても、利用者さんの笑顔や感謝の言葉を聞くだけで、何物にも代えられないほどのやりがいと誇りを感じることができるに違いありません。しかし、その行為の途中で転倒などの事故が起きてしまったら、善意に近い気持ちから出た行為が、今度は責められる行為に変わってしまいます。
今回のご相談に対し、直接的な、またノウハウ的な答えにはならないように思いますが、興味深い裁判事例が出ましたので、ここに紹介したいと思います。
家族による在宅介護を受けていた認知症の高齢者が、列車に衝突し鉄道会社に損害を与えたことにつき、子どもである長男に監督者に代わる監督義務違反があるとして、賠償責任が認められた事例です。2012年までの8年間で、認知症高齢者と列車との接触に関する事故は149件発生しており、うち115人が死亡していることを考えますと、高齢者の急増によってこのような事故が今後多くなることも予想されます。
具体的には、当時91歳で認知症を患う男性が、線路内に立ち入り列車に撥ねられ死亡したわけですが、そのために発生した列車の遅れや代替列車の手配、人員補充等にかかる鉄道会社側の損害を、亡くなった男性の相続人である当時85歳の妻や長男、介護福祉士であり特養併設の高齢者施設で勤務する三女らに対し、遺産の相続分に応じた金額の支払いを求めたものでした。
未成年者が引き起こした事故の損害部分を、親権者である保護者が代わりに支払う事例は過去にもありましたが、認知症高齢者が引き起こした事故の損害賠償責任をその子らに負わせたケースは非常に珍しいものです。ですが、超高齢社会となるわが国のこれからにおいて、高齢者の子の監督義務責任が問われることを暗示する事例でもあります。
この事例で裁判所が長男である子の監督義務違反を認めた理由として、当時91歳の父親に認知症の症状が進行し徘徊等があったにもかかわらず(要介護度4)、長男をはじめとする家族会議では特養に入所させる手続きもとらなかったことや、近くに住む介護福祉士である三女に対しても頻繁な訪問を依頼せず、訪問介護等の介護保険制度も利用しなかったという、在宅介護に必要な措置を講じなかったことによる判断です。
とくに私たちにとって関心のある視点としては、介護福祉士の資格をもち、高齢者施設で勤務している三女が、認知症で徘徊癖のある要介護度4の父親に対し、家族間というプライベートな関係であるにせよ、どのようなアドバイスや提案を行ったのかという点でしょう。
介護福祉士資格を持つ三女の民法709条不法行為による損害賠償責任の有無に関して、「―介護に職業として携わっている者として、認知症患者が徘徊して行方不明となる事例が多いことを認識し、徘徊中に交通事故等の事故に遭った事例も何件か見聞きしていたこと、家族会議においても父親を特養に入所させるかが話題になった際、特養の問題点を指摘して在宅介護を勧めながら、自己が父親の介護により深く関与することも、民間のホームヘルパーを依頼するなどして父親を在宅で介護していく上で支障がないような具体的な改善策を助言することもなかったこと、また、(父親が外に出ないよう)事務所出入口の事務所センサーに電源が入れられていないことを認識していたにもかかわらず、電源を入れる等の
徘徊防止等を講じておくべきと助言することもなかったこと」などから、認知症になった父親が自宅から独りで外出・徘徊して第三者の権利を侵害することのないような介護体制を整えておくべき不法行為法上の注意義務を負っていた、と結論づけたものです。
判決のバックグラウンドとして、相続人である家族ら介護者は、不動産を除く5000万円以上の預貯金を相続していることなどから、介護福祉士として近くに住む三女に、父親宅の訪問頻度を増やすよう依頼したり、介護保険の在宅サービスを利用するなどして在宅介護していく上で支障のない対策を具体的に講じなかった点や、父親が存命中、民間の介護施設や介護保険のサービスを十分に利用するだけの経済的余裕があったにもかかわらず、要介護度4の認知症である父親の監督義務を果たしていなかった、言い換えるならば、「相続するであろう分に見合った、十分な介護を行っていなかった」という結論に達したものと思われます。
今回紹介しました事例と、ご質問にある「法人の責任と、家族の責任」にひきつけて考えますと、いづれにせよ介護職に就く者としての専門性を示唆したものであったと思われます。先ほどの事例の場合、民法714条「責任無能力者の監督義務者の責任」との関係で、多額な相続を受けているという点と、介護のプロという視点から、家族が果たすべき介護のあり方を説いたものでした。一方、この高齢者が介護保険施設や、皆さんが勤めている介護サービス事業所で、行方不明になり列車事故を起こしたような場合であれば、プロである職業人集団として、法人に対し安全配慮義務違反があったと判断されます。
デイやショート、グループホーム等で認知症の利用者を預かっているケースでの争点は、徘徊行為と事故につながった過去のヒヤリ・ハッとや、行方不明にならないようなハード面でのセキュリティー(赤外線センサーやオートロック式の扉)をどう設置機能させていたのか、そして徘徊行為に対してケアプランまたは個別支援計画上での具体的な実施するサービス内容がどうなっており、それに対応した業務が展開され、記録化されていたのか、が職業人として求められる視点となります。
Q50. 都内の特養に勤務する生活相談員です。からすの先生、いつも連載を楽しみにしながら、施設内での研修で使わせて頂いております。4月からの新年度を迎えるにあたって、新人教育を実施しなければならない時期になるわけですが、施設内での事故が発生した場合、どの程度までの事故を家族に報告すればいいのか、迷っています。「その程度のことで、わざわざ連絡はいらない」と仰る家族もいらっしゃるのですが、ご家族への報告義務というのはどの程度のことを指すのでしょうか? 教えて頂けると幸いです。
A50. 日々の業務、お疲れ様です。利用されている本人を含めた、家族への報告義務は必要でしょうね。報告義務というよりも、説明義務と考えておいてください。そのことに関して、多少脱線するのですが、なぜ皆さんはクレームに対して拒絶感を抱くのか。たしかにクレームは誰だって嫌なものです。褒められるのとは訳が違いますから。クレームが嫌な理由としては、「ヤクザのように大声で怒鳴り散らすから」というのもあるかもしれませんが、結局は「面倒臭い」からなんです。では、何が面倒なのか。正確な情報を相手に伝えなくてはいけないからです。事故後のクレームなどでは、正確な事故の発生時刻、原因、誰が関係していたか、その方の既往歴等も頭に入っていなくては、十分な説明をすることができず、クレームを解決するどころか、不正確であやふやな情報によって逆に火に油を注ぎかねない展開にもなるわけですから。つまり、説明責任を果たすことの難しさですね。
質問に戻ります。どの程度(介護事故)までのことを家族に伝える義務があるのか、ですね。転倒や転落、誤嚥といった現象については介護現場では身近なものでありますから、イメージがつくのですが、介護事故やヒヤリ・ハッとの定義といったものはいまでも存在しない状況です。ですから、勤務されている法人や施設で、何をもって家族に連絡をすべき事故であるのか、の合意と統一を図っておく必要があります。
逆に、連絡や報告を怠ったために裁判となった事例を紹介したいと思います。正確には、連絡や報告を怠ったために、医療機関への搬送が遅れてしまったが故のトラブルです。医療訴訟においてはよく使われる争点の一つなんですが、「期待権の侵害」といわれるものがあります。一般的には、ある一定の事実や事象が存在する場合に、その事実から予測される法律上の利益が将来的に害された場合に争点となる表現です。最近の介護事故をめぐる裁判の争点には、必ずといっていいほどお目見えするキーワードです。
具体的な裁判事例からみてみましょう。事故当時78歳の女性が、平成21年7月17日 未明に施設内で転倒し、大腿骨骨折の傷害を負ったわけです。正確には、同日、午前5時30分頃、女性に体動があり起床したために、介護士が車いすで女性をトイレ誘導。女性は自力でトイレブース内の手すりを使って車いすから便座まで移動し、用を済ませている時に、「私、転んじゃったの」という発言があったわけです。その女性は、骨粗鬆症、認知症の既往歴があり、パーキンソン病、高血圧症、神経症、抑うつ状態、めまい等の診断を受け、パーキンソン病の重症度分類が4と診断されている方でした。施設長である医師は、家族を呼んで、医療機関での受診を介護スタッフに指示しました。家族が施設に到着したのがその日の夕方であり、その後、別の医療機関で大腿部の頸部骨折と診断されたのが、午後5時過ぎでした。その場合の争点の一つとして考えられたのが、転倒事故後の適切な対応義務違反に係る債務不履行責任でした。つまり、早朝に転倒し、大腿部の頸部を骨折していながら、半日以上も放置したという点です(東京地裁平成24年3月28日一部認容・一部棄却 控訴)。
また、最近のデイサービスをめぐる判決も、医師の診断を受けさせる義務をめぐって争われたものがありました。この事例は、事故当時87歳で、会話による意思疎通は十分にできた要介護度1の女性が、デイサービスを利用し、送迎車両から降車しようと席を立った際に転倒。翌日に大腿骨の頸部骨折が判明した事案で、速やかに医師の診察を受けさせる義務違反が認められたものでした(東京地裁平成25年5月20日一部認容・一部棄却 確定)。
具体的には、看護師である職員が、転倒した女性の右足のつけ根や腰の部分を確認した際、外傷や腫れ、熱感などの異常が認められず、女性が痛みを訴えつつも自力で歩行できる状態であったことから、医療機関への受診を行わなかったわけです。そのことについて医師に対し事故の状況やその後の症状等について説明を行い、転倒した女性の痛みの原因や必要な措置に関する助言を受けていれば、直ちに痛みを生じている部分を固定し、医療機関を受診するようにとの指示を受けることができたのに、翌日まで右足大腿部頸部骨折の傷害について適切な医療措置を受けることができなかったことによっての肉体的、精神的苦痛を受けたとして、法人側に損害賠償義務を課した事例でした。つまり、通所介護の提供を行っている時に、利用者の病状に急変が生じた場合、その他、必要な場合には、通所介護事業所側が利用者の家族または緊急連絡先に連絡するとともに、速やかに主治医または歯科医師に連絡を取る等の必要な措置を講ずべき義務を怠った、という内容です。ですから、事業所側には、事故を引き起こさないような安全配慮義務が課せられるだけではなく、事故後に適切なタイミングで医療機関に受診させなければならない義務までも負うということです。
ここで難しい点としては、高齢者なかでも認知症を患う方の場合、転倒等で大腿部の頸部骨折や圧迫骨折に到るような場合であっても、痛みや腫れ、熱などの症状が現れるのにタイムラグがあり、看護師を含めた医療関係者であったとしても、実際にレントゲン等で映し出さなければ骨折している事故であるのかどうか、微妙なケースが多々あるということです。ある例では、転倒により、確実に骨折しているだろうと病院に連れて行ったところ、医師から「たしかに圧迫骨折していますが、この一年ほどの間で複数回の骨折の跡がみられますよ」という言葉を聞かされることもあるわけです。介護スタッフからみて、利用者の軽い転倒であったとしても、必ず病院で受診させなければならないとすると、一日に何回、救急車を呼ばなければならないのか、というため息と同時に諦めにも似た感情が湧きあがることでしょう。
先の判決内容にもありましたが、「利用者の病状に急変が生じた場合」には、当然のことながら家族に連絡し、相談のうえで医療機関への受診という流れにはなりますが、「結果として」病状に急変があったとみられるような、見た感じでは分からなかったが、実は骨折していた、というような場合、誰が病状の変化を確定し、そのためにどのような情報から判断するのか、が非常に難しく悩ましい場面でもあります。
治療のために安静にして回復を待つという病院とは違い、高齢者施設を含め、今回の事例のような在宅介護サービスにおいては、高齢者の生活の一部としての機能を担っているわけですし、また自立支援という考え方からも、歩いたり、食べたりという行動への支援が業務の中心なわけです。ですから、積極的な展開を図ればはかるほど、転倒・転落や誤嚥のリスクは比例的に増す結果となります。
介護業界だけではなく、すべての産業界で、リスクの問題が信頼の問題にすり替えられているようなきらいがうかがえます。つまり、信頼関係が希薄になっているものですから、何等かの説明を行ったとしても、「そう言っているあなたは信頼できる人なのかどうか?」という見方を先にされてしまうわけです。介護現場でいえば利用者やその家族までもが低リスクを求めがちな昨今ですから、「説明責任を果たす」と同時に、信頼関係を育むような説明の仕方になっているのか、という視点も今後より求められるようになると思っています。
Q52. 東海地方の特養で生活相談員をしている者です。4月からの新人スタッフも、それなりに頑張っていますが、彼らの介助や記録の書き方をみていると、介護事故が起きた場合、家族に何ら言い訳できる部分がなく、不安でたまりません。実のところ4月にも、転倒や誤嚥で亡くなられた利用者もおりましたし、今後、ご家族との交渉が始まります。ご家族からは、何回かの面談の後、電話ではありますが「損害保険の方ではいくらになりますか…?」という質問があるくらいです。
からすの先生の連載を読ませて頂きましても、災害リスクへの対応にシフトしなければならないと思うのですが、介護事故が多く、いまは時期的にも余裕がない状況です。
介護事故について、新人職員にも分かるような事故防止策について、ご指導願えませんでしょうか。
A52. 日々のお仕事、本当にお疲れ様です。そうですね。私の研究所にも、介護事故に関する和解や示談の相談が非常に多くなっておりますから、ご質問にありますように、日々の業務のなかで余裕がなくなっている状況も理解できます。
また、この4月から入職したような新人職員にとっては、はじめてのことばかりでしょうから、実際に大きな事故に到らなくとも、ヒヤッとすることは頻繁にあると思います。新人研修等で、「裁判事例からみた介護事故の実態について話してほしい…」という依頼も多くありますが、新人職員に対し、あまり介護事故のリアルな実態や判決内容を伝え過ぎると、その恐怖感から介助に萎縮し、「リスキーな方の担当にならなくて良かった…」と思われるのも本末転倒なことです。だからといって、「事故がないように…」と、伝えないわけにはいきませんからね。ですから、新人職員に対しての介護事故防止に向けた伝え方には工夫がいることも事実です。
過去の連載でも何度かお伝えしていますが、「介護現場では事故は必ず起きる」ということを前提にしてください。それを利用者だけではなく、家族にも伝えておくことが必要です。自宅においても、転倒や誤嚥は施設での場合と比べて何倍もの危険性があり、また施設ではマンツーマンでの対応ができるわけではないことも。
では、どうやって、新人職員に対して介護事故の防止策を伝えるのか?
大規模災害時におけるBCP(事業継続計画)は、みなさんの施設や法人でも取り組まれていると思いますが、その手法が使えます。BCPつまり事業継続計画とは、何か大きなトラブルがあった際、介護のレベルといいますか、水準がガクッと落ちるのを半分程度までのダメージで抑え、その後の復旧について、もとの介護レベルに戻すまでの期間を短縮させる、という取り組みのことです。介護事故についても、大規模災害時と同様なダメージがとくに働く職員に対して発生しますから。たとえば、転倒事故が同時に複数発生するだとか、転倒・誤嚥事故でフロアーにいる職員が総出となって対応しているさなか、違う利用者の看取り介護も同時にしなければならない状況であるだとか…。そうなると、その場しのぎの対応では間に合わないだけではなく、その後の家族への説明を含めた対応についても、後手に回ってしまい事実確認すらままならない状況も考えられます。
大規模災害時におけるみなさんの施設で、リスクを考える際の図上訓練と同じように、5W1Hの視点から、標準的な模範回答ではなく、みなさんの施設に応じた独自の対応や課題の「気づき」を理解しなければなりません。その「気づき」や「課題」を十分に引き出すため、何を行うのか(WHAT)だけではなく、誰が(WHO)、いつ(WHEN)、どこで(WHERE)、どのような手段(HOW)で行うのか、そして、なぜ(WHY)その回答を選択したのかを、より掘り下げるための訓練をしておいて頂きたいんです。
では、具体的に事例から演習していきましょう。
要介護度3で、85歳の女性利用者が、昼食後、トイレに行こうと立ち上がり歩き始めたところで転倒。あまりに痛みを訴えるので救急車を呼び、医療機関に受診させたところ、右大腿骨頸部骨折と診断された。
分かっているのはこれだけです。図上訓練のように、5W1Hの視点から分析していきましょう。そのなかで課題も浮かびあがってきますから。誌面の関係で、何を行うのか(WHAT)、誰が(WHO)、いつ(WHEN)について説明します。
何を行うのか(WHAT)
「なぜ、事故が起きたのか?」を真っ先に考えるべきではありません。事故は必ず起きるものですから。必ず起きる介護事故について、なぜ起きたのか? を考えてみたところで、あくまでも結果論にしか過ぎず、職員個人の問題や素質、頑張りに原因があるかのような流れになってしまい、次に事故を防ぎやすい体制作りには決してつながりませんから。
まず、事故をされた利用者のケアプランを確認してください。とくに別表(2)です。その用紙には、左から課題やニーズ欄があり、右に向かって長期目標、短期目標、一番右端に実施するサービス内容欄があると思います。事故発生の直近のケアプラン別表(2)で、とくに「実施するサービス内容」と、直近1ヶ月前までの介護記録を整理する必要があります。ケアプランと記録との整合性が非常に大事になります。それから、過去半年程度の「ヒヤリ・ハッと」も過失責任を問う上で重要になります。また、要介護度3ということですので、認知症も含め過去の既往歴の確認を医師の意見書からまず確認してください。
誰が(WHO)
「トイレに行こうと立ち上がった…」ということですから、歩行介助の必要性があったのか、先ほどのケアプランや記録等で確認できると思いますが、四六時中の介助が必要のない方や、見守り程度の必要しかない方の場合には、その事故発生時もっとも近くにいた職員からの聞き取りや、その利用者が属するフロアの責任者が、その方のことを一番知っているはずですから、相談員レベルの職員が聞き取りを行う必要があります。何を行うのか(WHAT)の確認も、フロア責任者と相談員クラスの職員で行います。
いつ(WHEN)
事故発生後、事故報告書を作成する必要があるでしょうから、その報告書作成と同時に、上記のことを確認する必要があります。もちろん、家族へ事故発生の一報を入れた後に、家族への対応が必要となりますから、事故発生の一報後、家族との面談や交渉の前に準備しておく必要があります。時間が経つほどに記憶も曖昧になり、かえって自己防衛的な感覚も頭をもたげるものですから。なるべく事故発生後時間をおかないことが賢明です。また、医療機関に受診とありますが、転倒後、何時間後に救急車を呼んだのか、という点も非常に大事です。「期待権の侵害」といって、「もっと早い時期に病院に連れて行ってもらっていれば、こんなにひどくならなかったのに…」という家族からの訴えは、転倒・転落事故裁判では必ず争点になる部分ですので。
転倒・転落事故における過去5年間ほどの介護事故裁判の争点は、①「『ヒヤリ・ハッと』からみた過失の有無」、②「ケアプランと実施された介護記録との整合性」、③「リスクマネジメントに対する職員教員」、④「病院への搬送のタイミング(期待権の侵害)」、⑤「監督的立場(上司)にある者に対する指導義務」、⑥「適切な人員配置」となっていますから。
Q58. 関東地方の特別養護老人ホームで勤務する主任介護員です。いつも連載の内容を、月一回のフロア会議での研修に利用させて頂いております。最近とくに多くなっていますのが、夜勤帯に起こる利用者の転倒・転落事故です。もともと夜勤帯には職員の数も少なく、しっかりとした見守りもできるわけではありません。利用者がベッドから転倒した場合のダメージを軽減させるため、ベッドではなく畳等の使用も考えているのですが…。
転倒・転落のリスクについて、どこまで防ぐことができるのか、アドバイスして頂けると幸いです。
A58. 過去の連載のなかでも触れたところではありますが、「事故は必ず起こるもの」と考えて下さい。「事故をなくす」、「事故を減らす」という発想ではなく、「どこまでのリスクなら、負うことができるのか」という視点が必要になるわけです。
ですが、質問にあるような転倒・転落事故が頻発し、その度毎に家族から説明を求められ、クレームを含め鳴り続ける事務所への電話に対応することは、当事者である職員にとってかなりの負担になります。
最近の裁判事例から、夜勤帯に転倒・転落事故が発生した場合、施設側にどこまでの配慮が必要となるのか紹介したいと思います。
事故当時、人工透析もしており、認知症もあった81歳の男性が、深夜ベッドの脇に倒れ脳出血を発症して死亡したケースです。遺族となった家族側は、施設側の転倒・転落防止義務違反に基づく損害賠償請求をしてきたわけですが、転倒・転落防止の具体的な義務とは、①ベッドの使用ではなく室内に畳を敷き、その上に寝具を置いて転落の際の衝撃を緩和すべき義務、②消灯時間帯において、離床センサー等を使用して高齢者がベッドから転倒しないよう、もしくは自力歩行して転倒しないよう監視すべき義務、③ベッドの高さを低くするとともに、その周囲にマットを敷くなどして転倒時の衝撃を緩和し、負傷ないし死亡を防止すべき義務、④四輪の歩行補助具を使用させ転倒を防止すべき義務、⑤消灯時間帯
において、職員による頻繁な巡回体制をとった見守りすべき義務、⑥事故の発生原因やその対応、死因等に関する十分に納得できる説明をすべき義務などを主張し、①~⑥までを含めて転倒・転落の防止措置を適切に受ける期待権を侵害したことによる損害を争ったものです。
これに対して裁判所は、死亡した高齢者が排尿排便におむつを使用していたにもかかわらず、シーツだけではなく床や椅子にまで便が付くような状況にあって、ベッドに替えて畳を使用したり、ベッドの横にマットを使用することが衛生上の問題を引き起こす懸念があり、他の利用者も含め畳やマットの利用が、かえって転倒を引き起こす危険性があること等を併せ考えると、床に畳やマットを使用することが合理的であるとは言えないと判断しています。また、職員による頻繁な巡回等に関しても、日中はベッドの周辺を歩くことはあったにせよ、座位または臥位にてほとんどをベッド上で過ごすことが多く、就寝時には睡眠剤を使用しており、記録上夜中に目を覚まして歩いた様子が窺えないことなどから、転
倒することがあるかもしれないという予測可能性はあったにせよ、事故発生時刻である午前三時頃を含む深夜に目を覚まして歩き始めることまで、具体的に予測可能であったということは困難であるとして、巡回し見守る義務を退ける内容となっています。さらにこの点については、最近の介護・医療従事者をめぐる人手不足の問題にも触れ、かつ中山間地で過疎化が進む地域での職員確保の難しさにも言及し、事故当時の夜勤帯における人的態勢が直ちに不適切であるとは言い難いとしながら、事故当時夜間に概ね五回ほど職員が巡回していることを考えると、職員による四六時中の観察し続ける行為は不可能であると結論づけたものです。そして、利用者の転倒による死亡の原因や、死因を究明しなかった点、解
剖の提案をしなかった点、そして死亡事故直後における説明と、その後の説明とで若干の食い違いがあった点などから、遺族らが説明義務違反を主張した内容も退ける結果となりました。
過去、5年間程の転倒・転落事故裁判の原告側主張を整理すると、施設側に求めている内容が分かります。
●職員らが十分に見守りできる場所にベッドを設置し、適切に見守りをする義務
●転倒を防ぐため、ベッドの高さを低くする義務
●側面に手すりを設置する義務
●転倒時の骨折を防ぐために弾力のある床材を使用する義務
●ベッドの使用ではなく畳やそれに類する寝具を置いて転落の際の衝撃を緩和すべき義務
●離床センサーマット等を使用して高齢者がベッドから転落しないよう監視すべき義務
●職員による頻繁な巡回体制と見守りすべき義務
●事故の発生原因や、その対応、死因等に関する説明義務
●適切なタイミングで医療機関に受診(搬送)させる義務(期待権の侵害)
また、実際に裁判となった場合、上記の施設側に求められる義務に関連して、これらの主張を裏づけるための資料や根拠には次のようなものがあげられます。
○「ヒヤリ・ハッと報告書」、「事故報告書」の整理と提出(事故発生日までの当人における過去の「ヒヤリ・ハッと報告書」や「事故報告書」から、事故との因果関係を図るため)
○ケアプランと実施された介護記録との整合性(とくにケアプラン第二表における「実施するサービス内容」と、実際の介助内容、そしてその内容を記載した記録との整合性)
○リスクマネジメントに対する職員教員の実施体制(年間の研修計画等)
○監督的立場(上司)にある者に対する指導義務(職員間での説明義務も重要な視点)
○適切な人員配置(人員基準を満たしているのか、その配置に不備はないのか等の視点…人員配置上、人数的な不備はなくとも、たとえば誤嚥の恐れのある利用者への食事介助や見守りに、新人と実習生等のペアが適切ではない点など)
施設内の事故のなかでも、群を抜いて多いのが「転倒・転落」に関するものです。転倒・転落事故の多さについては、今も昔も変わりがありません。ですが、昔のように誠心誠意、利用者や家族に対して頭を下げ続ければ何とか許してもらえた時代とは異なり、これからは上記にあげましたような争点や、根拠に基づく介助が求められるわけです。
Q59. 都内の老人ホームでフロアリーダーを仰せつかっている看護師です。からすの先生の連載は、毎月の事例検討会議の締めくくりとして、法的な視点からのアプローチということで使わせて頂いております。
急に寒くなってきたせいもあるのでしょうか、転倒事故が毎日のようにあり、その対応に苦慮しているところですが、利用者の転倒後、どのようなタイミングで病院に受診させればいいのか非常に迷います。病院であれば医者がいますので、すぐに指示を仰ぐこともできるのですが…。アドバイスを頂戴できれば幸いです。
A59. そうですね。以前の記事にも書かせて頂きましたが、「同じ利用者が、ひと月の間に何度も転倒してしまう」という現象は、ごく当たり前のことです。それを介護職員の怠惰さや努力不足からくるものであると理解しないでください。事故が起こることの可能性や、マンツーマンの介護ではないことに加え、施設としてどこまでの努力が可能であるのか、可能な限り事故を防ぐために法人としてどのような工夫を行っているのか、を利用者やその家族に説明する責任が、今後より必要になると思います。
さて、転倒事故後の医療機関へのアクセスやそのタイミングについてということですね。
最近の転倒事故でも、医療機関に速やかに連絡し、医師の診察を受けさせるべき義務が争点になっているケースが多くみられます。「期待権」といわれる部類に含まれていると思いますが、よく医療現場で使われる考え方です。「適切な診療に基づく治療が行われていれば、救命された(後遺障害を残さなかった)可能性が極めて高い」と判断されたような場合に、適切な治療が行われることへの期待を裏切ったという発想のものです。介護現場での転倒・転落にひきつけて言うなら、「転倒や転落が起こった後、症状が治まっているように思えたので医療機関に受診せず、看護師の判断で様子をみることにした。しかし、その後の診断で大腿部頸部骨折や圧迫骨折が発見された。その間の数時間、母親は痛い思いをし続けたことで期待権を侵害した」という感じでしょうか。
高齢者がデイサービスの送迎中のバスの中で転倒し、看護師が利用者の足のつけ根や腰を確認し、外傷や熱感、腫れなどの異常所見が確認できず、また自力での歩行が可能であったことから、すぐに医療機関への診察が必要ではないと判断したものの、結果として翌日に右大腿部の頸部骨折が判明した最近の判例があります。このケースでは、利用者を常時見守るなどして転倒を防止すべき義務に対する違反については、「…排尿を済ませ、忘れ物を確認した上でデイサービスの車両に乗車した利用者が、職員において他の利用者の乗車を介助するごく短時間の隙に、不意に動き出して車外に降りようとしたことについて、これを具体的に予見するのは困難であり、介護のあり方として相当な注意を欠くものであったとはいえない」として、デイサービス側の責任を否定しました。しかし、医療機関へ速やかに連絡し、医師の受診を受けさせるべき義務には違反しており、期待権を侵害した、と判断しました。
その理由について説明したいと思います。まず、判決としては「(デイサービス側に)利用者である高齢者の生命、身体等の安全を適切に管理することが期待されるもので、介護中に利用者の生命及び身体等に異常が生じた場合には速やかに医師の助言を受け、必要な診療を受けさせるべき義務を負う」という前提に触れた後、転倒した利用者が痛みを訴えながらも、当日の午後7時と11時の2回にわたり自力でトイレに向かっていたことや、利用者の家族に事故の報告をした際も病院に連れて行くようにとの要望を受けていなかったことから、緊急性を要しなかったとデイサービス側は主張しました。しかし「…医師に対し事故の状況やその後の症状等について説明をした上で、利用者の痛みの原因や必要な措置に関する助言を受けていれば、直ちに痛みを生じている骨折部分を固定し、医療機関を受診するようにとの指示を受けることができたものと認められるから、利用者が翌朝まで右足大腿骨骨折の傷害について適切な医療措置を受けることができなかったことによって生じた肉体的精神的苦痛について、デイサービス側は債務不履行による損害賠償請求を免れない」として利用者や家族からの期待権の侵害について認めたものでした。
この期待権の侵害をめぐっては、2005年12月8日の最高裁判決が一つの基準となっています。ですが、この期待権については実定法上の定めがない抽象的な権利侵害の考え方でもありますから、利用者や家族が「過剰な期待」をしているような場合にあっては、医療・介護関係者に過度なプレッシャーがかかってしまうことに他なりません。ですから、冒頭でもお話ししましたように、施設として対応可能な範囲や、事故を防ぐために取り組んでいる点などの説明責任が問われるわけです。
今回の質問者が看護師であるという点で予備的にお話ししますが、先ほどのデイサービスの送迎車内での転倒事故をめぐっては、被告である法人側内部で、看護師である職員が利用者を病院に連れて行くようにとの指示をしなかった、と責任転嫁的な主張もあるのですが、裁判所は「看護師は被告側内部の人物であり、同人がその判断を誤ったことが法人側の責任を免ずべき理由とならないことは明らかである」として、一蹴したものでした。
このやりとりからしても、一見何ら外傷がないように思える転倒等の事故であった場合、「誰が何をもって医療機関への受診が妥当と判断するのか」が問われるわけです。老人保健施設とは異なり、特別養護老人ホームでは、医師が常駐しているわけではなく、例えいたとしても診察できるだけの処置室を有しているわけではありません。とくに認知症を患う高齢者の場合、骨折をしていたとしても症状を訴える能力が乏しく、さらに痛みや熱発等の症状が出るまでにタイムラグがある場合が考えられます。あるケースでは、利用者が介助中に転倒し、あきらかに圧迫骨折等を引き起こしているだろうと職員が思い救急車で入院のできる病院に搬送したところ、医師がレントゲン写真をみながら、「確かに骨折しているが、この1年の間に同じ個所が複数回骨折しています」という笑い話にならない話を聞いたことがあります。
では介護現場として、医療機関への搬送という視点から、どのタイミングでどのような判断をなすべきなのかについてお話しします。過去の連載にも書きましたが、介護事故についての定義は存在しません。「転倒・転落」や「誤嚥」といった現象があるだけです。介護保険法令の運用規定上にも「…利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合には、利用者の家族または緊急連絡先である後見人に連絡するとともに、速やかに主治医または歯科医師に連絡を取る等の必要な措置を講ずること」という規定しかありません。具体的なことは法人や事業所で定め、定められたことの「合意」が必要であるということです。つまり、どの程度のことを介護事故とし、どこまでをヒヤリ・ハッととするのか、といった事業所内での取り決めと同様、どの程度であれば看護師に相談すべき事象なのか、逆にいえば、どの程度までであれば現場のスタッフの判断で次の介助に移れるのか、という基準です。そして次に現場の看護師を含めた医療スタッフが、どの程度であれば自らの専門職の範囲内で処置しても許される範囲であるのか、また医師に連絡し指示を仰ぐべき事象なのか、それとも救急車による搬送をすぐにでも行わなければならないようなケースであるのか、の基準を施設内でつくり、その「周知」と「合意」が必要というわけです。